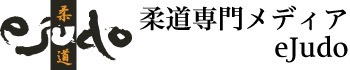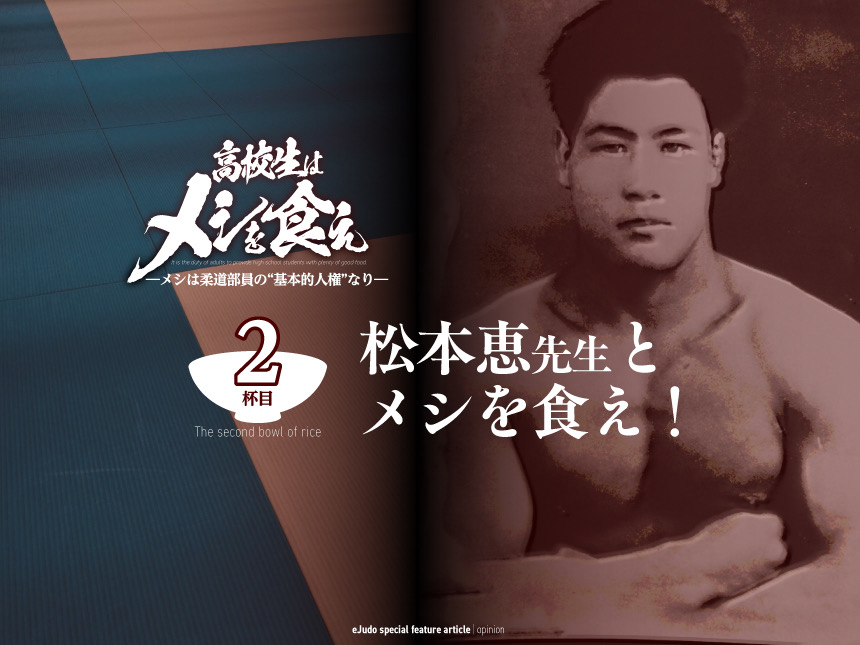
【第1回のあらすじ】「寮メシ」について実態を明らかにしなければ、と義憤に駆られた編集長(筆者)は、きちんとメシを食わせている学校の「寮メシ」を紹介することを決意。フードファイターとして編集部の体重140キロ小林大悟を召喚し、編集長との凸凹コンビでターゲットの学校に赴き、高校生と3食をともにすることとした。
* * * *
というわけで。まずは国士舘高校と東海大相模高校の「寮メシ」にお邪魔することが決まったのだが、ただ「旨い」「まずい」「多い」「少ない」と感想を述べていても仕方がない。楽しいは楽しいが、いくらなんでも底が浅すぎるだろう。そもそも高校生の運動部員はどのくらい食べればいいのか?何を食べればいいのか?きちんと食べられないと何が起こるのか? 評価にはきちんとした根拠が要る。
募集中の「あなたの寮メシ体験教えてください」アンケートを正しく評価するためにも、正しい知識を学んでおかねばならない。専門家の知見を頼りたいところだ。
というわけで、日本大学文理学部体育学科の松本恵教授を訪ねることとした。原沢久喜選手のパーソナル栄養士として全日本柔道選手権優勝・オリンピック出場を支え、日本大学柔道部の「食事」を監修。知る人ぞ知る「スポーツ栄養」界の巨人だ。
筆者はかつて「日大キッズ柔道」というイベントで松本先生が子ども向けに行った講習に参加したことがあり、そのわかりやすく本質的なアクティビティ(日大の屈強な柔道部員たちが食品に扮して、子どもたちに「このお兄さんは脂質だからこっちね」と三色食品群に仕分けられていました)にいたく感じ入ったことがあるのだ。いまでもその時の教えに従って冷蔵庫にはバナナとキウイを常備、朝は時々グリーンスムージーを作っては部活に勤しむ娘たちに振舞っている。久々、お会いできるのも嬉しい。
同大の金野潤監督に仲立ちを頼み「いまも松本先生は柔道部に関わっておられますか?」とお聞きしたところ、「関わっておられるどころか、いまはうちの部長ですよ!」とのこと。なんと!松本先生は日大の柔道部長になっていたのか。そして早速アポを取ったところ、快諾!
【第2回「松本恵先生とメシを食え!」】
というわけで秋田から呼び出した140キロ小林大悟と下高井戸駅前で待ち合わせ、徒歩で日大文理学部に向かう。
間の悪いことに私のiphoneで召喚したgoogle先生が物凄い回り道を選択し、結構な距離を歩くことに。世界選手権業務で1か月間ほぼ座りっぱなしだった直後、カンカン照りの東京の陽射しの中をPCバッグを抱えたままテクテク歩かされた140キロは、頭から足先まで水をかぶったように汗びっしょり。気の毒極まりない。「いくらなんでも少し拭いた方がいいですかね?引かれますかね?着替えも一応持っていますが」とフウフウいってうずくまる小林に果たしてどう声を掛けるのが一番面白いかと思案しているうちに、正門に松本先生が迎えに来てくださった。

早速研究室にお邪魔。ちょっとした撮影までこなせるキッチン付き、お洒落と実用性、そしてアカデミズムが融合した、非常に居心地の良い空間である。
まずはお茶を、とおもてなしくださる松本先生が小林に出してくださったウエルカムドリンクは「OS1」。いやもうお気遣いなく、などと遠慮していると「こんな状態でお茶ではダメです!これを飲んでください!」とバシっと一言。もう、このあたりから勉強である。かくて水分と電解質を得て熱中症の危機から逃れた140キロ小林ともども、さっそく質問の嵐を浴びせることとする。
「高校生の運動部員のメシの量・質」に国が定める基準はないんですか?

まずはここ。高校柔道部員には何を、どれだけの量食べさせなければいけないのか。寄せられた情報では明らかに「足りていない」「食わせていない」ケースがあるわけだが、例えばこれには国の、たとえばスポーツ庁などの基準(縛り)はないのか。あれば真っ向「おかしい」とバッサリ切り捨てることも、逆に「適切」と評価することも出来る。
松本先生曰く、これは「ある」のだという。
松本:厚生労働省が定める「日本人の食事摂取基準」がそれにあたります。0歳から75歳まで、年齢別・性別・生活活動強度別に、1日に摂取すべきエネルギー、各栄養素の推奨量を数値で示しています。学校給食や病院の食事は、これを基準に献立を作って提供されるわけです。管理栄養士が運営に携わる寮も、当然ながらこれを原則として献立を作成するはずです。
なるほど。「食事摂取基準」は日本人の生活の実情に応じて5年ごとに更新されるそうで、ちょうど今年が改訂年。陳腐さはなく、アップトゥデイトなものということになる。カロリーはもちろん、タンパク質、ミネラルの量までしっかり決まっているのだそうだ。厚生労働省のウェブサイトで公開もされている。では具体的に「部活高校生」はどのくらい食べればいいのでしょうか?
松本:スポーツ栄養の基本としては、エネルギーで言えば「1日3500キロカロリー(kcal)」を基準に考えます。3段階の生活強度で言うと、一番「強い」ですね。ちなみに、一般人は成人男性が2400kcal、女性が2000kcalです。
この基準から、競技特性や個々の発達段階に応じて増減を考えるとのこと。女子選手や審美系競技の場合はもっと少なくてもいいし、成長期であればプラスを考える。でも「成長期」って?
松本:「まだ背が伸びているか」を指標とします。身長が伸びていれば、20kcal~40kcalの蓄積量をプラスするのが基本の考え方ですね。
なるほど!
「食べ方」の注意点は?

おそらく「食べ方」も重要なはず。高校生の食べ方をみていると、スピードから「順番」から、かなりまちまちである。この点気を付けることはあるのだろうか。当方に前提となる知識が少ないので、敢えてWhatできいてみる。
きちんと食べるためには、稽古から考え直す
松本:体を大きくする(増量)を考えているのであれば。まず、食事の前に水分をたくさん取り過ぎるのはダメです。水をたくさん飲むと食欲が減退しますし、消化能力も栄養の吸収能力も下がります。胃腸が冷えてしまうんです。
とはいえ、練習の後にはやはり喉が渇く。終わるなりガーっと水分を取るのは、私たち「稽古中水を飲んではいけない」世代柔道部員のあるある風景。稽古後、水をたくさん飲んではいけないんですか?
松本:そもそも、練習やトレーニングの後に物凄く喉が渇いている状態であることがよくありません。練習中の水分補給が上手くいっていない証拠です。失った水分・塩分と体に入れる分のバランスがきちんと取れていれば、あとは練習後にちゃんと体温を下げることで、上手に食べられるようになります。これがうまく行っていなと、体が熱いまま、喉が渇いたままで食事に移行することになるので、どうしても冷たいものを取りながら食べることになります。脱水と熱中症状態のまま食事に臨んでいるということですね。いわゆる「水バテ」。食べられないし、食べても栄養を吸収出来ないので体は大きくなりません。
なんと、「食事は稽古から!」。そこでピンときた。実は、事前調査で寄せられた情報で「アイスクリームを食べながらご飯を食べる」部員がいるという話があったのだ。ネタ枠で使おうと思ったが、ここは早速聞いてみる。この選手はいかがですか?
松本:間違いなく「練習中の水分補給がうまくいっていない」状態です。おそらく体温が下がっていない。たぶんその選手、薄着で食事していると思います。そして「アイスを食べながら食事する」これは胃腸をアイシングしながら食事するようなものなので、当然消化・吸収に良くない。
解消するには?
松本:先ほどお話しした通り、練習中からきちんと水分を取って、うまく平衡状態を作っておくことです。そうすると、練習後のアイシングやシャワーで体温管理を適切に行えますので、食事もきちんと摂れるようになりますし、栄養も効率よく摂取出来ます。
「体を大きく出来るか」は、食事云々ではなく、稽古の段階で決まっているということか。メシトレではなく本命の「トレ」こそがメシトレということか。水分・塩分の収支を合わせて、しっかり体温を下げてから食事に臨む。ということは、松本先生、日大では食事を作るだけでなく稽古にも介入を?
松本:しました!(笑)こちらはいかに選手にきちんとご飯を食べてもらうかしか考えていないわけで、そうやって考えていくと、これはもう練習からだな、と、そこに踏み込んでいくしかなかったんですよ。練習にもしっかりついて、適切な塩分・水分補給を行ってもらうようにしました。
水分補給。ここで摂取すべき水分とは?筆者が取材する中では、「スポーツドリンクは稽古、朝トレは水でいい」というような例も見ました。
松本:やはり暑くて発汗があるときには、糖分・ミネラルを含んだスポーツドリンクが安全だと思います。運動時はスポーツドリンクを選んだほうがいいです。逆に、食事の合間は水やお茶で十分です。
「食べる順番」でコントロール
練習をがっちりやり、一生懸命食べても大きくなれない選手は結構いる。他にこういう選手が気を付けることはあるのだろうか。
松本:線の細い選手は、水や牛乳のがぶ飲みで食べられなくなっているということが多いですね。牛乳はたんぱく質や脂肪が満腹中枢を刺激するので、それ以上食べられなくなってしまいます。あとはプロテインも満腹中枢を刺激してしまうので、順番を変えたほうがいい。ご飯をしっかり食べようと思ったら、カゼインとか筋量を増やすタイプのプロテインは、食後にしてもらった方がいいかと思います。逆に言うと、減量する人はこういったものでうまく満腹中枢を刺激して、食事を減らすことは可能です。ただ、高校生くらいで体重を増やしたい選手は、やってはいけませんね。
「順番」が大事。他に、食べる「順番」で気を付けることはあるのだろうか?私は普段、まず野菜から食べることを習慣にしている。しかしこれは一般的な、どちらかというと中年以上の健康にフォーカスしたものの気がする。運動部員の場合どうでしょう?
松本:仰る通り。野菜から食べる所謂「ベジファースト」はよく言われますが、これをやると早くお腹が一杯になってしまいます。体を大きくするのであれば、ご飯と主菜をまず食べて、野菜は「順番」でOK。消化吸収を良くするには汁ものの出汁(だし)、アミノ酸がいい。ですので、味噌汁やお吸い物にまず口を付けるのがいいでしょう。
「筋肉量を増やす」系の大人界隈でも、トレーニング後「先に繊維(野菜)を取らないように気を付けろ」と言われると聞いたことがある。なるほど!
高校生がきちんと食べる意味
「高校生にきちんと食べさせる」がこの連載のテーマ。そもそも、高校生の時期にきちんと食事を摂る、ということの意味、なぜこの時期が大事かということを聞いておきたい。先生、いかがでしょう?
松本:筋肉・骨格の発達に一番良い時期なんですね。この時期に栄養が足りないとしたら非常に勿体ない。せっかく背が伸びる・筋肉が発達出来る用意が整っているのに肝心の材料が足りないということですから。量はもちろん、しっかり栄養を摂ることが物凄く大事です。また、将来体を強くするための嗜好の柔軟性を形成するうえでも、物凄く大事な時期だということもわかって欲しい。20歳くらいになると、食事の好みというのはなかなか「治らない」。まだ若く、考え方や好みが柔軟な時期に色々なものを食べるというトライアルアンドエラーが必要なんです。これが偏ってしまうと、いざアスリートとしてもう一段上がろうとなった時、キャリアを決める最も大事な時期に「これを食べなさい」「こういう食べ方をしなさい」と指導されても、出来なくなってしまうんです。
なるほど。例えば栄養が満たされていたとしても、同じメニューが極端に繰り返されるような環境はあまり良くないということですね。これも「寮メシ」の考え方としてかなり大事です。
松本:ルーティンとして固まってしまったものを、20歳過ぎてから改善したり変更したりするのはかなり難しいことなんですね。家庭の教育の中であれば柔軟に育っていけるはずのこういう素養が、養われないとしたらそれは勿体ないことです。考え方が柔軟な時期に色々なものを食べる、「食」の上でもさまざまな経験を積むことが、体を強くして競技を続けていく上ではとても重要だということはわかって欲しいですね。
第1回で話題に挙げた「小林(料亭の息子)が大きな怪我をしたことがない」ことについても聞いてみた。子どものころから良いものを食べているから怪我をしにくいという仮説だ。大きい怪我に苦しむ選手は、そもそも高校時代から細かく怪我をすることが多い印象。また、取材している感覚としては「怪我が多いチーム」が偏っているという印象も、確実にある。「いいものを食べていると怪我が少ない」、これ、あるのでしょうか?
松本:怪我をするのは「足りていない」「負担が掛かっている」からだと言うことは出来ますね。骨や筋肉を強くしていくための材料が足りていないというのがまず1つ。あとは、ビタミンやミネラルが足りないと、「不定愁訴」というのですが、集中力がなくなったり体調不良になったりします。なんとなく元気がない、眠い、だるい。格闘技は一瞬の気の緩みが大怪我に繋がりますから、この部分はよく考えて欲しいですね。
松本恵先生というひと

ここで、あらためて松本恵先生という人を紹介しておきたい。日本大学には15年前に赴任。すぐに金野潤監督から「柔道部のサポートに関わって欲しい」と声が掛かったとのこと。もっとも大きな使命は「原沢久喜選手の体を大きくすること」だったが、加えて力を注いだのはチームサポート。柔道部全体の栄養状態を良くすることはもちろん、何を食べて何を飲むのか自体が「物凄い戦略になる」と訴え、これをマネジメントさせて欲しいと自ら申し出て大会の現場にも入っていた。
松本:学生優勝大会で勝つことをプランするのであれば、決勝含めて5試合を勝ち切らなければならない。1時間おきに全力運動が入るわけで、この間、どのタイミングで何を食べて何を飲むのかはまさに「戦略」です。しかし、監督・コーチ・選手は他にも考えることが一杯あるんです。極めて忙しい。いくらわかっていても、飲み物や食べ物まで的確にマネジメントすることは、なかなか出来ない。この部分では、私に限らず専門家を入れてもらうとまったく変わると思います。
日本武道館のアリーナレベルにアクレディ(ID)カードをつけた栄養士が入る。これはさすがに異例だったのでは?
松本:初めてということでした(笑)。私の仕事自体、最初は学生にも、コーチにもなかなか理解してもらえなかったですね。強い選手であればあるほど、それこそ高校で自分のやり方を作って来ていたりしますから。「そんなもの飲んだことがない」と拒否反応が来たりする。これを「とにかく言われた通りにやってみてくれ」とお願いして飲んでもらう。そうすると、わかってもらえる。「最後の試合のパフォーマンスが全然違う」「次の日の疲れ方がまったく違う」と理解してもらえるようになる。これを毎年繰り返していました。東部(直希)選手なども、このルートでわかってくれるようになってくれた1人ですね。最初は頑なでした(笑)。
松本先生は原沢選手のパーソナル栄養士としても有名。選手1人に専任で栄養士がつくという体制は、当時としてはかなりの異例。大きな話題になった。
松本:選手個人に専属で栄養士がつき、海外の試合にまで帯同してご飯を作るというのは、それまでにはなかったと思います。ただ、柔道競技というジャンル自体には、「栄養」を重視して理解する下地があったんです。上村香久子さんが長く全日本柔道連盟の管理栄養士を務めていたこともあり、他競技よりは入りやすかったと思います。
原沢選手の2度目の全日本選手権優勝が、もっとも嬉しかったという松本先生。研究室には当時の「近代柔道」が飾られていた。「あの時は、栄養的な面からもかなり分厚くサポートしたのですが、これが物凄く上手く行って、彼も『勝たなきゃいけない』と感じてくれていたと思います。少しプレッシャーになったかなというくらい」と、笑顔で当時を振り返っていた。
いまの日本大は、松本先生に選手としてサポートを受けた世代が、コーチとして入閣。松本先生や、現在食事の監修に携わる同大の吉沢幸花助手が「自然にサポート出来る」環境が整っているとのこと。ちなみにこの取材の直後、日本大は全日本学生優勝大会で28年ぶりの優勝を飾った。もちろん当日は吉沢栄養士も帯同してサポートしていたそうだ。あの決勝の選手たちの逞しい戦いぶり、無尽蔵と形容すべきスタミナと、体の強さ。この日の取材でお聞きした松本先生の「何を食べて何を飲むのか自体が物凄い戦略」という言葉を思い起こさずにはいられなかった。
いまが過渡期かもしれない。「寮メシ」格差の時代

高校の「寮メシ」。酷い話もたくさん聞くが、筆者の知る限り、きちんとやっているトップ校もある。
指導者の意識も上がっている。数年前、全国高校選手権決勝で富士学苑高校の選手が敗れたことがあったのだが、話を聞きに行った矢嵜雄大監督は何よりもまず自分を責めていた。「ガス欠。おにぎり1個ぶんのエネルギーが足りなかった。補食が足りなかった。ここで必要なんだときちんと説得して摂取させなかった自分の責任。選手はまったく悪くない」と。
また、国士舘高校の百瀬晃士監督は言う。俗にいう「夏の国士舘」、これは食事の強さでもあると。夏になったからと言っていきなり食べさせても力がつくものではない、と。1年通じてしっかり食べさせて体を作り、エネルギーを蓄え、それをもとに追い込むから夏に頑張れるのだと。他のチームが疲労してシーズン最終盤に実は力を落とすことが多い中、最後まで戦い切れるのはここだと。日々のきちんとした食事があってこそ、夏の追い込みにも耐えられ、「強さ」も発揮出来るのだと。
指導者がこういうことを真っ向言える時代、なぜ前時代的な「寮メシ」がはびこるのか。このあたり、松本先生の「いまの日大はかつて選手としてサポートを受けた選手がコーチに入っており、理解がある」という話からは「知見」のほかに、「世代」の問題を強く感じるところでもある。
松本:仰る通り、指導者の世代は関係しているかもしれませんね。大学時代に選手として科学的な栄養サポートを受け、食事がいかに身体づくりや競技人生に影響を与えるかを実感した世代が、指導者になって現場に戻って来始めたのがここ数年。ここを大事なポイントと理解出来ているかどうかは、大きな違いになっている可能性があります。
もちろん経済的な事情、学校の理解度とさまざまな変数があるのは理解の上だが、これは重要な指摘だ。高校生の栄養管理はいまが過渡期なのかもしれない。筆者は肌感覚で、学校ごとにかなりの差を感じている。もっとも「食」に「格差」のある時代。それがこの2020年代中盤なのではないだろうか。
「減量」について
柔道競技は体重別制。「減量」という話題は避けて通れない。栄養学に見て「減量」という行為はどうなのだろうか。ここも率直に聞いてみた。
松本:スポーツ栄養士の立場としては、「20歳以下の減量は控えてもらいたい」というのが率直な意見です。その後の競技寿命を考えても、選手の健康を考えても、良くない。若年の時に減量をして飢餓状態を作ってしまうと、糖尿病など生活習慣病になりやすいです。特に飢餓状態と食べることを繰り返すのは、本当に止めて頂きたい。精神に与える影響も大きいです。
筆者は成長期が遅く、高校2年冬から3年に掛けて急激に体が大きくなり、知識のないまま過酷な減量をした。「減量失敗で試合に出られない」悪夢でうなされて泣きながら目が覚める、これがなくなるまでその後20年掛かった。
松本:そうなんです。神経が発達する時期に心と体に負担を掛け過ぎるのは、その後の人生にも物凄く影響します。成長期は体だけでなく、心への負担も大きい。こういう大きな負担を掛けるような行為は絶対に避けるべきです。20歳を過ぎ、ストレス耐性が出来上がった大人になってからの「きついこと」はある程度超えていけるもの。成長期の振る舞いとは厳に分けて考えて欲しいですね。
ついでに「お酒」について
かつて、金野潤監督から、日大で松本先生が選手相手に行った講習会の様子を聞いたことがある。松本先生が「言っておきますけど、生理学的にはお酒は『毒』でしかないんですからね!」と発すると、学生たちが一斉に下を向いていたと。今回は高校生対象の企画ではあるが、ついでに「お酒」についても聞いてみた。すると、松本先生の目がギラリと光った。
松本:スポーツ栄養士としては、お酒はアスリートにとって、完全に排除していいものだと考えます。仰る通り、生理学的にはまったくもって「悪」でしかありません。脱水する、筋肉の保守・修復を妨げる、グリコーゲンなど糖分の蓄積を妨げる、肝機能も落ち、タンパク質も落ちる。いいことはないんです。「ノミニケーション」とか、リラックス効果を狙うということであれば、他の方法を考えるのが理想ですね。アスリート本人だけではなく、コーチやマネージャ、メディカルスタッフも協力してアルコールを取らない体制を構築すべき。そもそもの選手生命、スポーツマンシップなども考慮して、アルコールは排除すべきだと思います。
たまさか、先日雑誌にこの件についてかなり厳しい意見を書いたところなのだという。「臨床スポーツ医学」2025年6月号、「ハイパフォーマンス発揮に向けたリカバリーの科学と実践」。読むと「百害あって一利なし」とズバリ。最後は個人の判断だろうが、考えるにあたって己の「軸」は持っておいて欲しい。興味のある方はご一読ありたい。
親御さんも読んでください!「差し入れ」は何を持っていけばいいのか?
一気に色々な知識を得た。なんと有意義な時間であったことか。そしていよいよあすからは「寮メシ」行脚スタートである。
メシを頂くからには、差し入れを持っていきたい。そしてここまで話を聞いたからには、意味のあるものを持っていきたい。ここで松本先生に聞かない手はないだろう。松本先生、高校柔道部への差し入れは、どんなものがいいのですか?
松本:「もっとも欠乏しやすいものは何か」から考えるといいかと思います。そしてそれは間違いなくビタミン。疲労してビタミン不足だと、すぐに病気になってしまいます。フルーツがいいでしょうね。選手は食べるのに手間がかかること、具体的には「剥く」ことを嫌う(面倒くさがる)傾向にあるので、簡単に食べられる果物がいいでしょう。キウイ、みかん、いまの季節ならやや高いですけど、さくらんぼや、手づかみで食べられるいちごもいいですね。蛋白質であれば、定番の鯖缶や冷凍の「牛丼の具」など。
なるほど。そしてまた、これも多くの関係者にとっては皮膚感のあるシチュエーションだと思うのだが、たとえば遠来の保護者が試合に差し入れなどを届ける場合は、どんなものがいいのだろう。
松本:これ、結構気に掛かっています。インターハイなどに行くと、特に女子チームなどでは、親御さんが地元のスイーツを大量に買って差し入れ、畳にどばーっと甘味が広がっていることもしばしばです。試合期間なのに、そうではないよな、と。ぜひ「手間なく食べられるフルーツ」を検討して欲しいですね。私も試合場にはフルーツサラダを良く持っていきます。あとはエネルギーを考えてカステラ。あんぱん、和菓子もいい。洋菓子はクリームたっぷりで脂肪分が多かったりするので、避けた方が無難です。胃もたれの原因にもなりますし、せっかく取った糖分、水分の吸収が遅くなります。
カステラ!そういえば、羽賀龍之介選手など、トップ選手の間では試合日の補食としてカステラが大人気と聞く。ずばり「カステラがいい」理由は?
松本:カステラを最初に柔道界に持ち込んだのは、私だと思います。流行しているのであれば、ありがたいことです(笑)。卵と小麦粉と蜂蜜と砂糖だけで出来ています。小腹がすいているけどおにぎりは重い、ゼリーでは足りない、というときにちょうどいいんですね。1日中ゼリーだとなんとなく辛くなってきます。そういう時にカステラ。あと、お団子はおすすめです。
もう、勉強になることばかり!
ここで松本先生への質問会はおしまい。短い時間ではあったが、実に濃密であった。単純に物凄く面白かった。こんな企画を立ち上げたものの、やはり知らないことばかり。勉強になった!というしかない。松本先生、ありがとうございました!

というわけで「真面目回」終わり。あとは高校生とメシを食うばかり。140キロ小林を宿に返し、私は差し入れを手配に回る。最初のターゲットは東京都の名門・国士舘高校。いよいよ「寮メシ」3食フードバトルの開始である。
高校生よ、メシを食え!!!!!
文責:古田英毅
Text by Hideki Furuta
スポンサーリンク