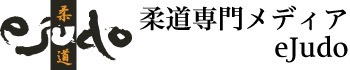→東京オリンピック柔道競技完全ガイド
文責:古田英毅
Text by Hideki Furuta

「なぜこんなに勝ったのでしょうか?」
既に73kg級評で書かせて頂いたが。東京五輪終了後、「なぜ日本はこんなに勝ったんでしょうか?ひとことで答えてください」という質問を受けることが多い。非常に難しい。ひとことで返すなど無理なのだが、筆者の場合は「準備の質が良かったから」と返すことにしている。今回の日本代表は金メダルを獲れる力を養うことを目指すのではなく、既に金メダルを獲る力があるものが「絶対に失敗することなく、確実に金メダルを獲る」ことに徹底的にリソースを費やした。かつて目標であった力を養うことは大前提、その先にある「研ぐ」作業、「詰める」仕事に数年間を費やした。これまでになかったことだ。だから、これまでにない成績が出た。
もちろん論理的な強化計画、連盟のバックアップ、風通しの良い文化、所属と代表の円滑な連携、科学研究部の情報分析とその活用、徹底したコンディショニング、そして選手の高い意識、と勝利の理由を挙げるのであればマクロからミクロまでそれこそ枚挙に暇がない。膨大であり、網羅的に書くのは筆者の力量では難しい。ただ、この一事が実現出来たことに全てが集約できるのではないかと思う。勝つために力を上げることではなく、力のあるものが絶対に失敗せずに勝つためにリソースを注ぐことが出来た。体制も、制度も、計画も、人も、マクロからミクロまで同じ方向を向いてこの実現にすべてを収斂させていた。勝因は、これに尽きると思う。
代表候補プロテクト策、1年延期による「内省」
「力を養った上で、確実に勝つことにリソースを注いだ」。今回金メダルを獲った9名が全員既に世界選手権での優勝経験がある、つまりは「力」を証明済みの選手であることにこれは端的だ。髙藤直寿、永瀬貴規、大野将平の3名が初めて世界を獲ったのはリオ五輪前。彼らは大げさでなく「確実に勝つ」こと1点のみに5年間すべてを費やしたと言っていいのではないか。
他6選手の世界選手権制覇がいずれもリオ後の3大会であることからは、日本代表が「力を上げる」という難しい大前提をまずきちんとクリアしたことがわかる。そして金野―井上・増地体制の5年間が、大きく言って、この、力のあるものたちに、確実に勝つために己を「研ぐ」時間と環境を与えるという方向で一貫していたことは疑いがない。
最たるものは、早期代表内定制度である。強化はかねてまず講道館杯の免除枠を広げて(参加者のレベル高く人数多く、日本で最も難しいこの大会で万が一負けたらキャリアがいったんリセットされてしまうことが、かつての強化選手たちにとっては大きな負担だった)代表クラスの鍛錬期と、強化の機会(国際大会参加)を確保する方向性を打ち出していたわけだが、2017年から(2018年バクー世界選手権の選考から)は、ついに「選抜体重別(4月)までは代表を決められない」という積年強化と選手を苦しめて来た枷をも外すことに成功した。世界選手権の優勝者がグランドスラム東京(11月・12月)で優勝した場合はその時点で翌年の代表内定という新制度である。加えて東京五輪本番では、「逆転不可能な差がついた」として4月を待たず、2月の欧州シリーズ終了の時点で13階級の代表を決めた。一に、「確実に勝つ」ための研究と調整、「研ぐ」時間の確保のためである。選手もこれに応えて、他から狙われることを大前提に、ライバルたちをもう一段突き離すべく成長を続けた。
そしてこれは強化のトップたちが皆一様に認めているところであるが(大会後に個別に多人数をインタビューさせて頂いた)、コロナ禍による一年延期が実に大きかったと見る。大会に出られず、時期によっては稽古すらままならずひたすら自己を見つめたその「内省」が大きかったと彼らは口を揃える。納得である。確実に勝つため、己の力を出し切るために必要なことは、何より己を知ること。足りないものは何か、「狙われる」のはどの部分なのか、これを埋めるためには何が必要なのか、相手が想定する自分の戦い方は何か、その上を行くにはどうすればいいのか、そして何より、自分のもっとも強い部分とはどこなのか。これを徹底的に考え抜き、己を鍛えたことが、効いた。
日本代表以外の金メダリストは90kg級のラシャ・ベカウリ、100kg超級のルカシュ・クルパレク、48kg級のディストリア・クラスニキ、57kg級のノラ・ジャコヴァ、63kg級のクラリス・アグベニューの5名。うちクルパレクとアグベニューは世界タイトル保持者なので、今大会は14階級中11階級で世界王者が金メダルを獲った大会ということになる。加えてクラスニキとベカウリは優勝候補の一であり、ジャコヴァはメダル確実圏の選手。大外から捲って金メダルを獲った選手がただの1人もいない。荒れることが大前提の五輪としては異例と言っていい。コロナの1年間、強者が内省を利かせて隙を埋め続けた1年間は「強いものがより強くなる」結果を生んだと言っていいだろう。(加えて、まだあまり言われていないが、無観客試合であったことも「強いものが勝つ」結果にそれなりの影響があったと思っている。あの磁場が歪むような熱狂が会場になかったことと番狂わせの少なさは無関係ではないはず)
① 候補選手のピックアップと複数プロテクト強化→②世界選手権勝利による力の証明と選手の選別→「③確実に勝つ」詰めの作業
この流れが上手く行ったこと。そして③の重要性をこれまでにないほど強く意識し、時間、環境、人的リソース、すべてを注ぎ込めたことが日本代表の勝因だ。「力を上げる」ことではなく「確実に勝つ」ために力を注いだ5年間。日本は勝つべくして勝ったと言っていい。
高い意識の継承と浸透を
今後立ち向かうべき課題は、いわずもがな。五輪代表選手たちにほとんど文化として染みついた「単に力を上げるのではなく、確実に勝つことにリソースを投じる」「己が強くなることだけでなく、どうすればそれが発揮できるのかを最大限思考する」という思考・行動規範が、2番手選手以降に薄いことだ。日本代表最大の勝因を、文化として共有しているグループの人数が極めて少ない。2番手・3番手選手を派遣した6月のブダペスト世界選手権における代表選手たちの戦いぶりは、(丸山城志郎ら優勝した選手、一部の選手を除く)これが同じチームの選手とはにわかに信じがたいほど。結果以上に内容が厳しかった。力云々ではなく、思考の方法論や方向性自体に断絶を感じた。もちろん、この大会の内容を見て五輪代表が修正を掛けたという面もあるだろうが、まさに「強くなれば、勝てる」「自分の良いところが出さえすれば、勝てる」という、力があってもなかなか結果が出ないかつての日本代表の姿、一種いきあたりばったりとすら言っていい試合が非常に多かった。
コロナ禍における海外との環境差が大きすぎて選手にとっては気の毒な面もあったが、そこに寄りかからず、この断絶の構図が可視化されたことを幸運と考えなければならない。これは一種必然の現象だ。五輪の成功はまさに前述挙げた通り、「①候補選手のピックアップと複数プロテクト強化→②世界選手権勝利による力の証明と選手の選別→③『確実に勝つ』詰めの作業」という流れがきちんと踏めたことにあるが、いま起こっているこの文化的分断は成功のスタート地点である①、「少数傾斜強化」の副反応であるからだ。以後の強化から代表選手以外が排除されてしまった。
特に3番手以降が薄い。代表の文化を濃く浴びていないだけでなく、そもそも国際大会の経験自体が少ない。
この5年間は、トップクラスが強くなり続けた5年間であるとともに、下から突き上げようとするものがなかなか国内から脱出できない、飛び抜けたもの以外はなかなか機会自体を得られない厳しい5年間でもあった。一例を挙げると。現行制度下の国際舞台へのゲートは、グランドスラム東京である。出場枠は各階級「4」。同年の世界選手権出場者にこの権利が優先的に与えられるわけだが、世界選手権で2枠代表が行使された階級であれば(14階級中4階級)、残枠はこの時点で「2」。そして他の強化選手に優先的な枠の付与がある年であれば(たとえばアジア大会優勝など)、講道館杯開始の時点で参加者に与えられるグランドスラム東京出場枠は「1」しか残ってない。新たに国際舞台の一線の洗礼を浴びられるものが年に1人しかいないという状況は、強化の間口としてかなり厳しいと言わざるを得ない。この枠にぎりぎりで漏れたものが講道館杯上位入賞者としてGS東京-欧州ハイレベル大会(パリ・デュッセルドルフ)以外のマイナー国際大会に派遣されてたとえ優勝したとしても代表選考の正ルートには入っていけず、あくまでその経験は「単発」、評価は「参考」に留まる。実績としてまったく次に繋がらない。1度トップグループに入ったものの権利が守られてなかなか脱落しにくい一方、新規参入が極めて難しい。また、シニア中堅層が分厚過ぎて、他国が組むような「世界ジュニアをステップとしたワールドツアーでの出世」という別の登攀ルートがなく、国際大会に適性のある若手が出遅れがちであることも問題だ。いままさに経験を積んで適性を試されるべき素材、他国であればどんどん国際大会に出て強くなっていけるはずの特に若い社会人選手が、出るべき試合自体がなく所属でお茶を引いている。ワールドツアーが爛熟したこの5年間で国際経験の重要性が増したこと、そしてコロナ禍によって国際大会参加自体が激減したことがこの断絶構図を一層増幅。いまや1番手と2番手、そしてこれらトップグループと3番手以降の経験・力量の差は史上かつてないほど開いていると言っていい。
強化の方法に、どの時代も共通の絶対に正しい方法などというものはありえない。現強化体制が既存の制度を大きく変え、新たな方法を積極的に取り入れたのはまさにそのためだ。そして最終的に採った少数グループ集中強化方式は、「リオー東京期」の世界と日本の実情に、そしてどうしても勝たねばならない地元五輪というミッション達成に対して、これ以上ないと言っていいほど適切な策だったと思う。
これが一定の成功を収めたいま、今度は次の「いま」に向いた新たなやり方を考えなければならない。日本代表成功最大の因が「目標と実情に適ったもっともいいやり方(制度)を、考えて実行した」柔軟な態度自体にあることを忘れてはならない。まず具体的には、ワールドツアーのレベルが上がったことと国内の人材供給の将来的な目詰まりを見据え、制度的な門戸を広げて、中堅・若手、幅広い層に国際大会を経験させること。この実現に動かねばならない。

鈴木桂治氏を男子新監督に迎えた新強化体制(金野―増地・鈴木体制)は、既に監督就任会見でジュニア・カデ世代の強化を最重要課題の一に挙げている。伝え聞くところによると、コロナ禍の穴を埋めるべく、また選手層の厚みを増すことと3番手以降の若手の強化を考えて、かなり大胆な派遣も検討していると聞く。筆者ごときが言うまでもなく、この点十分に考え抜いているということだろう。クリアすべきハードル (具体的にはまず第一に予算の確保)が非常に高く、また多岐にわたる問題なのだが、果たしてどんなやり方を見せてくれるのか。とても楽しみだ。
そして何より大事なのは「継承」。「リオー東京」期を戦う過程で生み出された「強いものが失敗せずに絶対に勝つ」ための具体的な方法論、ものの考え方を次の世代の選手に伝えることだ。これは今後の日本代表の核になるであろう、東京五輪チームの貴重な成果物だ。いままでの日本代表が「個」の経験則でしか得られなかったものを、組織として開発したと言っていい。「いままでにないことをやったから、いままでにない成果が出た」その最大の因を単発で終わらせてはならない。おそらく組織にはこの文化も方法論も残る。伝えるべきは、選手1人1人だ。選手の特徴は個々それぞれ違うが、「ものの考え方」の基本は同じはず。今回の大勝で金メダリストたちが見せてくれたアプローチはかなり本質的なもの。日本人の「勝負」という概念自体の位相を引っ張り上げるだけの実(じつ)がある。常に成長を止めないこと、考えることを止めないこと、そして何より己というものを理解すること。歴史的大勝がただ1回の現象で終わるのではなく、次なる大勝の礎となるよう、今回得た知見を着実に次の世代の選手たちに植え付けてもらいたい。
スポンサーリンク