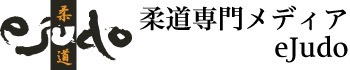文責:古田英毅
Text by Hideki Furuta
70kg級
もっかの担ぎ技系優位は生態系のコントロールミス

常々考えていたトピックである「現代柔道競技(ゲーム)における担ぎ技系の構造的な強さ」。これが語りやすいのが70kg級。今回あらためてこれを思う試合が多かったので、このタイミングで出しておきたい。
今のルールとその運用は「担ぎ技系」に有利。極端に「掛け数」を重視することに加え、捨身技に厳しく担ぎ技に甘い偽装攻撃の反則裁定基準がこれを加速している。「組み合って投げ合う」という2013年以来のIJFポリシーの、「組み合う前に掛けてしまう」という形での抜け道になっている。抜け道を見つければ、人は当然そこを広げに掛かる。もっかツアーで大流行中の「ぶらさがる片袖背負投」などはこのルートに特化したものだ。
非担ぎ技系(二本持たないと技術が表現しにくい)は、片手でもひとまず掛けられる担ぎ技系を前にしては、己も「片手でも掛けられる技」、少なくとも「片手でも掛けられる崩し技・展開技」を持っていないともはや同じ土俵に上がることすら出来ない。構図としてはあっていいのだが、あまりにも非対称性が強まり過ぎた。プレビュー記事を書くにあたって、相性や戦力に基づいて具体的な試合の進行を考えると「順当であれば、手数を積める担ぎ技系が勝つ」という予測で収められてしまう試合の多さにあらためて驚く。全日本選手権の予想座談会でも近い構図があった。
内股系や大外刈系の選手は、もはや二段も三段も上の強さがないと担ぎ技系と戦うことが出来ない。技術が噛み合わない。同じレベルだとやれない。生存競争(ゲーム)における有利不利の傾斜がここまで強まると、当然ながら生態系そのものに食ってくる。環境に対する進化適応の必然として、生態系のメインストリームは「担ぎ技系」になる。この状況を放置すると、近い将来「柔道競技」には担ぎ技系しかいなくなってしまうのではないか。競技で表現出来る「柔道」の技術の幅が極端に狭くなりつつある。かつて「タックル柔道」の横行を受けてIJFが足取りを禁じた理由は、柔道競技のアイデンティティ (投げに特化した結果生まれた多種多様の投技技術体系)を表現する場が奪われてしまうくらいに「技術の非対称性(有利不利の傾斜)」が強まってしまったからだが、それに近いところまで来つつあると思う。
70kg級はこれを語りやすい
行きつ戻りつで恐縮だが、なぜ70kg級でこれが見えやすいかについて。一般的な担ぎ技による先手掛け潰れを直接的に封じる手段として、「二本で体幹を止める」ほか、「掛け潰れを捨身技(抱分・引込返)で切り返す」「寝技で仕留める」がある。特に「寝技」はしっかり出来ていれば物凄く有効。しかし70kg級は、寝技のレベルが高くない。寝業師と呼べる選手が少なく、平均レベルも明らかに低い。東京五輪におけるメダリスト同士の戦い、マディーナ・タイマゾワ対新井千鶴戦の長い寝勝負が端的だ。
この階級はパワーがあって投技に威力のある選手が多い。IJFが本来推奨して来た「組んで投げ合う」という指針に近いトライブの選手が多数生息している。それでも、この種族は勝てなかった。優勝したのは「掛け数」モードをベースにする担ぎ技系のマルゴ・ピノ、掛け数に戦略を振れる「担ぎ技系」の手札の、非担ぎ技系に対する非対称性が物凄くわかりやすく出た階級だった。
どちらが強いかの話ではない

この「担ぎ技系に極端に有利なルール」。単に試合の勝敗ではなく、ジャンルの魅力をどう表現するか、という大きいステージでの問題であることを強調しておきたい。「柔道」という大きな円で包まれた技術体系の魅力を、その中のより小さな円である「柔道競技」というゲームでどう表現させるかという大戦略の話だ。この観点で考えた場合、「表現できる技術が1つの技術に偏る」仕切りは致命傷のレベルで、良くない。
57kg級のホ・ミミvs出口クリスタ、70kg級のマルゴ・ピノvsマリー=イヴ・ガイ、同じくマルゴ・ピノvs田中志歩、同じくマディーナ・タイマゾワvsエリザヴェト・テルツィドゥ。いずれも今のルールにおける「担ぎ技系と非担ぎ技系」の非対称性がモロに出た試合だった。ピノは担ぎ技系としても到達点が高くきちんと投げて試合を決められる人だが、ホはまだそのレベルになかった。徹底的に担ぎ技系と非担ぎ技系の非対称性を拡大すること、つまりはタイプの「相性」だけで勝った。あの57kg級決勝を見て、良い・悪い・強い・弱いを超えて「柔道の魅力が存分に表現された」と考える人はたぶんほとんどいないだろう。
阿部一二三に「あの勝ち方」を強いるルールでいいのか
筆者が長く触れて来た話でいえば、「阿部―丸山」状態がわかりやすい。どちらも極限まで強くなったがゆえに、タイプの非対称性が露骨に出る構図となった。それぞれのタイプで強くなり過ぎてノイズがまったくなくなり、結果実は単なるタイプによる「じゃんけん」(タイプの噛み合わせだけで勝負が決まる)構図になった。組まないと表現が出来ない「非担ぎ技系」丸山城志郎に対し、組ませないままでも技を出せる「担ぎ技系」阿部一二三が一方的にゲームの優位を取ることになった。
阿部の勝ち方がどうこうという話ではない。阿部一二三という物凄く強い柔道家にこの勝ち方を「させてしまう」今の柔道競技の「仕切り」(ルール)はどうなんだ、という話である。誰がどう見たって、阿部が背負投、丸山は内股とお互いの持てる技術を発揮しあって、その上で強い方が投げて勝ったほうが面白いに決まっている。そういう高所から「仕切り」を考えたときの話である。
マディーナ・タイマゾワは「ルールに壊された選手」

この観点から。70kg級で銅メダルを獲得したマディーナ・タイマゾワは、「ルールに壊された選手」だと思っている。柔らかい身体と強い体幹を駆使、伸びのある内股も仕掛ければ、接近戦には裏投や横車などの大技を繰り出していた、あの面白い選手の柔道がまったく変わってしまった。掛け数がベースの担ぎ技系にモデルチェンジ、加えて流行りの「肘で膝を外側から抑える」技術に傾倒して、背負投崩れで肘を突っ込んでは隅落や小内刈で倒れ込むことを繰り返す、つまらない選手になってしまった。度々この技で相手を負傷させているが、この傾倒は変わりなし。今のルールでどう戦えば成績が残せるか、「環境」(ルール)に適応して戦い方を変えた結果である。ルールは競技が進む方向性を指し示す。そしてルールは、選手を作る。いまのルールが示唆するのは、タイマゾワ型の選手の製造だ。こんなもの、はっきり言って、全然豊かじゃない。
では「崩し技」や「展開技」は柔道の魅力の表現に必要なのか?
ルールはルールなんだから、選手はその中で勝てる方法を考えなければならない。非担ぎ技系はきちんと対抗する手札を持たねばならない。これは正論である。ご存じの通り筆者はその派。先手攻撃に特化した担ぎ技系に対峙するには展開技や崩し技を駆使して二本持つ事が必須と常々説いて来た。むしろ組み手と連動して「展開技」や「崩し技」を駆使できないトップ選手は失格、こういった技術を単なる掛け潰れ技と区別出来ずに闇雲に否定する解像度の低い指導者もまったくもって失格、と思っている。
ただ、その筆者にしても「では、これは柔道や「投げ」の本質に本当に必要か?」となると首を傾げざるを得ない。崩すことでしっかり組めたり、あるいは本命の投げに繋げたり、と「次に繋ぐ」技術はまだいい。ただ、単に「指導」を取る(取ることでその後の相手の行動を縛る)ための技術は、本来の「投げる」行動と直接的には関係がない。こんなことをしなければ同じ土俵に立つことすら出来ないという仕切りに、もろ手を挙げて賛成するというわけには到底いかない。
草の根は敏感、偏狭な少年指導者や親はとっくに気づいている
掛け数重視のルール、先に掛けられる技術の圧倒的優位。何を難しいことを言うのかという向きがあるかもしれないが、実はこの構図にもっとも敏感なのは草の根だ。一部の少年指導者や親だ。安易にまず片手技(一本背負投)を教える。「やりやすいから」「投げる感覚を優先させたいから」、さまざまな言い訳をつけて教える。全体利益には適わないが、己が生き残るための戦略だからそもそもそこは視野にない。そして環境の傾斜に適応した結果なので生存競争には強い。これが厄介。少数であってもこういう価値観の人たちが混ざることで、実は生態系全体が壊される。一部の識者には「少年カテゴリの一本背負投を禁止するべきではないか」という声があると聞くが、筆者もまったくもって同感である。安易な勝利至上主義であるとか、その後の本人の成長を妨げるとか(どちらも当たりである)という以前に、それが柔道修行者の生態系全体の破壊行為に他ならないからだ。筆者は柔道に対するテロリズムであるとすら思っている。小学生が、練習して来た己の技を発揮出来ないのはまだいい。力が足りず、投げられて負けることもいい。ただ発揮する機会そのものを拒否され、しかも目の前で「その偏狭な人たちが自分に勝った」絵を押し付けられる。これはきつい。そんなつまらないジャンルを続けるものはいない。(もう1つ言うと、これで勝った側はその後伸びない。勝ち負けにだけフォーカスしている以上、やがて多くが辞める。結果柔道をやるものは誰もいなくなる)
「突き詰め切ったトップ」の構図は、実は「始めたばかりの初心者」にもっとも端的に投影される。どちらもノイズがないからだ。トップはすべてが出来るがゆえに、初心者は出来ることが少ないがゆえに(大事なことしか教えられていないがゆえに)、属性の特徴がモロに出る。「小中学生とトップは違うんですよ」という説明は通用しない。むしろもっとも連動している。いまの状態がジャンルの危機だと、柔道人は強く自覚すべきだ。
ではどうするのか
まだこれという決定的な提言は出せない。あまりに事態が行き過ぎたがゆえ、また時間制限がある中で原稿が「ある」ことを優先するがゆえ、粗さも完成度の低さも、そしてただ批判するという行為の片手落ちも飲み込んで、ひとまず出させて頂いた。すぐ出来ることとしては、担ぎ技の偽装攻撃をきちんと取る、少なくとも捨身技なみの基準で取るという「運用」。もっと長いスパン・大きな構図の改革としては、たとえば偽装攻撃の反則は取らない、消極的試合姿勢の反則も取らない、掛け数も重視しない。その代わり「効果」を認める。徹底的に「有効な投げ」の有無とその優劣だけで勝負を決める。もう1つ、「寝技の攻防も攻勢として認める」。(寝技で攻めることが出来るのは、実際には立技で十分に崩した場合だけ=寝技の攻勢は有効な投技があったことの証明になり得る)(流行中の「ぶらさがる背負投」は返すことすら難しい。寝技で取るしかない)
未整理だが、大きくこの方向でものを考えるのはアリだと思う。
成長していた田中志歩、2度目の世界選手権は別物

田中志歩は銅メダル。優勝こそならなかったが評価はポジティブ。内容が良かった。タシケント世界選手権時の、自分の長所を見誤って大技を仕掛けず、しかも手札が少なくそれを埋める術がなかった様とはまったくの別人。技の種類が増え、ゆえに戦型の幅も広がり、採れる選択肢が増えたゆえであろうか、驚くべきことに戦術眼も上がった。神は細部に宿る。技術の精度が上がること、使える技術が増えることで、これをコントロールする「戦術眼」自体も上がった。戦略・戦術・技術の成長は補完関係にあるのだ、ディティールからタクティクス(戦術)、そしてタクティクスからストラテジー(戦略)という「ボトムアップ」のルートがありえるのだとあらためて確認出来たようで、実は感動すら覚えた。田中は戦略・戦術面が弱い選手ではなく、実は使える手札が多くなかっただけ、そして手持ちの札の意味が整理されていなかっただけなのだと、よくわかった。そして実戦に追われながらではここまで中身の濃い積み上げ・内省は逆に出来なかったはず。苦しい負傷欠場期間は無駄ではなかった、田中のキャリアにとっては実はこれ以上ない「鍛錬期」になったのでないかと、そこも胸に迫るものがあった。
ピノ戦は、ここまでつらつら書いて来たとおり、ロジック(ルール、もっかの競技におけるタイプ的な非対称性)で負けただけ。掛け潰れに甘いIJFのルール運用で形上負けがついただけだ。柔道は勝っていた。次回に期待したい。
78kg級

「個別種」ヴァグナーの圧倒的な強さ
そして78kg級は2021年の世界王者アナ=マリア・ヴァグナーが圧倒的な強さで優勝。凄まじく強かった。今春のツアー序盤戦で見せた「大内・小内」を中心とした組み立てには「これをやったら誰も勝てない」と思わせるくらいの威力があったが、その後はほぼ使わず。不思議に思っていたものだが、やはり単に封印していただけだった。今回は積極的に投入、使っているターンは手が付けられなかった。一番長く戦ったのが、GS延長戦1分3秒「指導3」の濵田尚里戦。GS延長戦に縺れ込んだのはこの試合と決勝だけで、ほかはすべて本戦決着。「一本」連発で頂点に立った。
凄かったのは、前述の「担ぎ技系の構造的有利」を1人で跳ね返したこと。決勝、アリーチェ・ベッランディの担ぎ技連発に対し、身長182センチ(公式データ。実際にはもっと大きく見えるのだが)を誇るその体が折れ曲がること一切なかった。すべて背筋を伸ばして跳ね返して、得意の内股に大内刈、大外刈と伸びのある技で投げに出続け、最後は窮して掛け潰れを繰り返すベッランディを送襟絞で絞め落としてしまった。
逆にいうとヴァグナーくらいのモンスターでないと、この非対称性は跳ね返せないということなのだが、本当にやってしまうのが凄い。先ほどの「環境への進化・適応」という話でいえば、ヴァグナーは、ネズミ算式に増える「適応種」に、己1匹の力で逆らっている「個別種」だ。引き手をまず逆手に構えることでスタートするなど(おそらく、把持したときに内から外に回して絞りを強めること、相手の腕が内側に入ってくるのをブロックすることを目指している。担ぎ技系対策にもなっている)、採る手立てのディティールも面白い。この優勝でパリ五輪代表にも決定(恐ろしいことだが、ドイツは本当にアリナ・ブーンとここまで競らせたらしい)。本番の大暴れが楽しみだ。
良い出来だった濵田
濵田尚里について。ヴァグナーに敗れたが、内容は近来にないほどよかった。クオリティが高かった。徹底的に釣り手を殺し、狭く入れ、振り向きながら刈り開く大内刈で取りに出た。大きく言えばやはり立ち技でヴァグナーに勝つことは難しかったということになるのだが、その立ち技がシンプルに強くなっていたし、作戦も良かった。ノーシードで、ヴァグナー直下を引いてしまったことだけが厳しかったというだけ。まだまだやれると思わせる大会だった。
打ち合いベース、やはり面白い階級

78kg級は今回も、やはり面白かった。ベスト4にヴァグナーとベッランディ、マドレーヌ・マロンガが残り、3位決定戦にオドレイ・チュメオが勝ち残ってと、個性ある役者がしっかり勝ち上がって持ち味を発揮した。ベースはあくまで「打ち合い」。仁義なき「一本」王国、78kg級の面目躍如である。余談ながら「個性」という観点では、チュメオが凄かった。3位決定戦はすぐさま投げて「技あり」、そのまま袈裟固に抑え込んだのだが、なぜか引き手を引かずに頭だけ下げて返されてしまい、そのまま逆に抑え込まれて一本負け。強いが不安定、いつも最後に「何かを起こしてしまう」チュメオの本領発揮。審判までその空間に引きずり込まれてパニックに陥っていた。78kg級を語る上で、やはり外せない人である。
スポンサーリンク