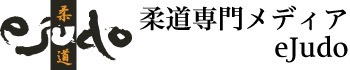文責:古田英毅
Text by Hideki Furuta

いよいよパリオリンピックが開幕する。リオ・東京の前に出したほどボリュームのある原稿ではないが、この大会を、競技史的な視点から位置づけておきたい。
柔道競技の技術は史上最高レベルにある。爛熟期である。間違いなく2024年7月のこの時点が、過去最高到達点と言えるだろう。実はこれまで柔道競技の技術レベルは時間軸に比例して直線的に上がり続けて来たというわけではなく、上がったり下がったり時に停滞したりの変動を繰り返して来た。現在はかなり角度の鋭い上昇期、そして到達した高みは間違いなく過去ナンバーワンだ。
そして、この上昇カーブがこの先も続くかどうかはまったくわからない。「爛熟」という表現を使わせていただいたが、実はまさに「熟れて落ちる」寸前の可能性もある。今回の五輪は「ワールドツアー時代」という幸福な時代を象徴する大会であるとともに、時代を区切るマイルストーンになる可能性があるとみている。
柔道競技はどう面白くなったのか
改革のツールは「ルール」と「環境」
「負けない組み手」と「印象点稼ぎ」が戦術のメインストリームになった2012年のロンドン五輪の柔道競技が“まったくもって面白くなかった”という危機感から、IJFは種々様々の策を取った。
手段はまず「ルール」。旗判定を廃し、ギアを変え(持ちやすく技が掛けやすい、薄くてタップリとした柔道衣を採用した)、「投げ」を際立たせるために足取りを禁止し、「指導」差決着を廃止。組み手回りは「持ち合うこと」(互いに投げに発展する可能性がある状態)を大方針に据えたアップデートを常態化、幾度もルール変更を繰り返して競技者に「投げる」ことによる決着を促した。
もう1つの手段は「環境」。ワールドツアー制度を整備し、世界各地を舞台としてビッグゲームの定期開催を期した。同時に2014年からはJUDOBASEを立ち上げ、ワールドツアー全試合の結果と映像を格納。技術の相互研究と拡散を可能たらしめた。
結果、ざっくり言って柔道競技(すくなくともワールドツアー世界の)は物凄く面白くなった。「ルールが選手を変える」の象徴的事例としては王者テディ・リネールを挙げることが出来るだろう。かつて組み手による封殺で「相手に何もさせない」ことを志向、圧倒的なフィジカルを「指導」差勝利に全振りしていた彼が、2017年以降は投技の獲得に振り、直近の世界選手権2大会では強烈な投げを連発して優勝。34歳にして「リネール史上」もっとも投技のレベルが高く、もっとも魅力的なスタイルを身に着けている。

生態系に何が起こったか
新技術移入が盛んに起こった「ロンドンーリオ期」
「ルール」と「環境」。この2つを手立てとした改革で、この10年で何が起こったか。
「ロンドンーリオ期」(2012~2016年)の柔道競技は、民族格闘技の博覧会の様相を呈した。モンゴルは所謂「やぐら投げ」に代表されるようなモンゴル相撲の技術を、ジョージアはチダオバから密着系の技を、イラン(当時)のサイード・モラエイはイランレスリングから「モラエイ」(反り投げ)を持ち込んだ。足取りというカウンター技術がなくなり、かつ密着戦や「絞り合い」といった「持つ」前提の形にアドバンテージを持つ技術が大量流入した。カザックレス(カザフスタン)やクラッシュ(ウズベキスタン)といった民族格闘技を持つ中央アジア勢の躍進がこの時期に起こったことも、偶然ではない。柔道競技は、これら民族格闘技の五輪における発露の場としても機能した。。
同時に、クラシックな柔道技術の大量復古が起こった。特にカウンター技にこれが顕著だった。すべてを解決していた掬投(この技術の先鋭化は00年代の柔道競技の方向性の1つの象徴だ)が使えなくなり、ほぼ死に体だった横車や抱分が復古し、引込返や浮技の有用性が上がった。これらの技が前述の民族格闘技勢の強さの源泉である、「パワー」と相性が良かったこともこの復古に一役買った。
次に来た波は「技術の標準化」
次に来た波は、これらの技術の吸収と、「標準化」である。ワールドツアーの大量開催とJUDOBASEに代表される映像情報の提供により、たとえ特異であっても、有用な技術はあっという間に標準化することが当たり前になった。民族格闘技の技術も間を置かず「柔道競技」の技術体系に吸収された。少し旧い技術で恐縮なのだが、今の高校生に「やぐら投げ」がモンゴル由来の技術で彼らの代名詞、ほんの10年前にツアーでこれが決まる様は衝撃的だったと話してもなかなか信じてもらえないだろう。しかも、この「技術の発見と拡散」、そして「対応」というスパンは年々早まっている。2018年の時点でも、フランク・デヴィトが「脚を持たないハバレリ(帯取返)」で勝ちまくったら、1か月後の大会では対応技術である「アゼルバイジャン式浮落」の猛威にさらされて今度は連敗という事態があった。開発-対応―標準化のスパンが極めて速いワールドツアー時代を象徴するエピソードと言えるだろう。
相手に対応するためには、技術を知らなければならない。己をよく知る相手を乗り越えるためには新たな技術を身につけなければならない。どんなに威力のある技があっても、それ1つだけに偏っては絶対に勝ち続けられない。「1回だけ勝つ」のではなく安定して強者の位置に座るためは、研究と開発というアップデートのスパンをひたすら繰り返すほかはない。柔道競技全体のレベルはかくして、爆発的に上がった。過去、偉大な王者や突出したテクニシャン、あるいは彼らを取り巻くグループ数名が今を超える高みに到達することはあったが、「全体」のレベルがここまで上がることは皆無であったはずだ。
「相手にどう振舞わせるか」戦術の手札が爆発的に増えた
技術が上がると、当然ながら状況の解像度も上がる。これまでなんとなく見送っていたはずの絵に幾通りもの角度から解釈が為され、戦術のレベルが上がる。打開のために手札が増える。
防御のレベルも上がった。攻撃技術それぞれに付随するリスクがマップされた結果、選手が準備なくいきなり「無茶攻め」に振ることは難しくなった。守備に全振りした相手を投げることは難しい。余裕を持って待つ相手にはカウンターも食いやすい。この「なかなか技が決まらない」状況を打破するための種々様々の試みがもたらした最大のものが、「指導」奪取の技術のレベルアップだ。
スコアの傾きで相手の振る舞いをコントロールするために「指導」を取る。具体的には、相手が無理をしてでも攻めて来なければいけない状況に追い込んだり、多少悪い組み手でも受け入れざるを得ない状況を強いて、己の投げが決まりやすい状態を作る。つまり「指導」をいわば「作り」のツールとして使う。そのためには、己の攻めが止まる状況を作ってはならない。手詰まりが起こる状況を作ってはならない。己の技術体系の中に「苦手な状況」を作ってはならない。どんなときでも「投げれなくても攻め、攻めることが次の投げに繋がる」ことが必要になる。幣サイトの戦評記事で頻出する「股中体落」や「引き手で近い襟を握った前技」「片手内股」「片手対角の大外刈」「蹴り崩し」などはこういった、攻めながら状況を上げていく「展開技」の典型例だ。
悪い状況だからと言って、1回1回組み手を切ってやり直していては(少なくとも国際では)勝てない。ゆえに「相手が受け入れやすい状況(ある程度組ませる、絞らせる)を利用する投げ」も当たり前になったし、「無茶な技を掛けさせて後の先の技で取る」作りや、誘いの技術(実は投げの準備は出来ていて、スイッチを押すだけだが一見不利な形)の精度も上がった。いまやツアーの柔道競技は、単に乱取りが強いからといってその技術体系を「知らない」ものが軽々に足を踏み入れられる世界ではない。
ワールドツアー時代の「方向性」
整理しきれずまだまだ書ききれないのだが、いったん置く。この「ワールドツアー時代」の柔道競技を体現する選手が、81kg級で世界選手権連覇中のタト・グリガラシヴィリ(ジョージア)だ。組み手、投げ、寝技と全方位のパラメーターが極めて高い。ロンドンーパリ期の柔道競技が示す方向性の完成形と言ってもよいだろう。緩急自在、最終的には「投げて解決」の攻撃柔道が持ち味。丁寧な組み手と担ぎ技を軸に戦う安全運転モードと、密着して強引な腰技や左小外掛、裏投を狙う勝負モードを使い分ける。一発で状況を変える足技も持ち、寝技も得意。手が詰まる状況が一切ない。しかも単に手札を繰り出し続ける小賢しいタイプとは一線を画し、「ここが勝負」とみればリスクを飲み込んで一発勝負に出る度胸もある。かつては抱き勝負一辺倒の選手あったことでもわかる通り、アップデートを止めることもない。今のルールで勝ち続けることを突き詰めたら、最終的にはこうなるしかないのだ。こういう選手の出現は、IJFの改革、2012-2024の「ワールドツアー時代」の方向性の論理的帰結である。女子では「出来ないことがない選手になりたい」と自ら語り、進化を止めない52kg級の絶対王者・阿部詩が同じ位相にある。
(実は先んじてここに到達した選手に、ファンがこれぞ日本柔道の体現と熱狂した大野将平がいる。大野に関してはそもそもこの時期のIJFのルールの改廃が「こんな選手が理想的」とモデルケースに据えた匂いが濃い。より大きい文脈で「ワールドツアーの柔道」に関わった選手であるとリマークしておきたい)

この爛熟は続くのか?
2024年は上半期だけで実に9つのワールドツアー大会が開催され、この5か月という短い期間だけでも、新たな技術が持ち込まれ、標準化され、対応されるというスパンが密度高く繰り広げられた。昨日の必殺技は今日の標準技術、過日の穴は本日の罠。ワールドツアーはまさにいま、熟れている。
ただし、この爛熟が続くとは限らない。
この隆盛を呼んだ2つの手立てに、曲がり角が迫っている。
まず「ルール」。IJFはパリ五輪後に大規模な改正を考えているとの情報がある。(技術が上がり過ぎたことによる)ゲームの膠着にメスを入れたがっていると伝え聞く。具体的には、限定的な「足取り解禁」があるのでは、という噂を聞くことが増えた。もちろん確たる情報ではないのだが、もしこれが本当に起こった場合、この先競技はどちらの方向に転がるかわからない。「脚を持つ」技術の復古が始まり、弱者に一発逆転の可能性が与えられて試合がエキサイティングになる一方で、これまで強者が「続けて勝つ」ために磨いた種々様々の技術が無力化されていく可能性がある。
次に「環境」。ワールドツアーがこの先、どれだけの規模で維持できるのかどうか疑問だ。柔道ワールドツアーはマネタイズ出来ていない。放映権料で潤っているわけでもなく、開催国の金銭的負担が大きい。IJFは「JUDOTV」のサブスク化など手を打とうとしているが、状況は厳しい。残念ながら、少なくとも開催国が先を争って誘致するような魅力的なコンテンツにはなっていない。こういうものを「持ち出し」で誘致出来る国は限られる。実際に、ツアー創設時に比べて開催国は明らかに偏っている。いわゆる「西側」の民主主義国家は減り、資源国かつ覇権主義的な「お金が出しやすい国」に傾いている。開催地域もいきおい偏る。南米・北米・アフリカ地域での開催大会はいまやほぼゼロだ。それはそれでいいという考え方もあるだろうが、大げさにいえば「気持ちひとつで成り立っている」IJFやこういった国々の持ち出しがいつまで続けられるのか。
「Never Miss The Throw!」
というわけで、2024年7月のいまは、さまざまな状況が噛み合った一瞬の「最高到達点」なのだ。ひょっとすると10年20年経って「グレコローマン柔道の総決算」と位置付けられる大会になるかもしれないし、「いちばんレベルが高かったころ」と振り返られるかもしれない。もちろん新たなハイレベル柔道競技の出発点となった大会と総括される可能性もあるだろうが(そう願いたい)、いずれにせよ、「ワールドツアー時代」を区切るマイルストーンになることは間違いない。
長々書いてきたが、言いたいことは「一瞬たりとも見逃すな」ということである。IJFのスローガンを借りれば「Never Miss The Throw!」。歴史的な大会を、目を凝らして楽しもう。観るもの全員が、柔道競技史の証言者である。
スポンサーリンク