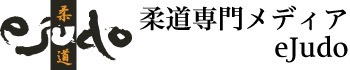文責:古田英毅
Text by Hideki Furuta

新井道大のダイレクト反則負けについて。当日発信のタイミングを逃したのでレポート記事で触れるつもりであったが、ここだけ先に、別項として書いておく。
先に要旨を示す。
・新井道太は世界選手権の銀メダリスト。世界選手権と同じように振舞ったに過ぎない。
・相手は背中どころか尻すら接地していない。なので「背を着いた相手を引き上げて叩き落す」、所謂“バスター”、”パワーボム”の反則は対象外。ぶらさがった相手を制し落としたのみ。
・ゆえに審判がこれにダイレクト反則負けを宣するのは誤審。テクニカル的には完全な「シロ」。
・ただし(ゆえに)審判委員、審判長の説明は「バスターではなく“柔道精神に反する行為”での反則負け」
・国際大会と国内大会のルール運用の差が生みだした事態だった。
・新井をこの挙に出させるだけの蓄積があった。今年度学生優勝大会の「指導」を取らない審判姿勢は異常。
・「柔道精神に悖る行為」の適用も、「指導」を取らない姿勢も、国際と国内のルール運用の差を「言語化して明示していない」ことが引き起こしたものである。問題は同根。
・国際大会と国内大会のルール運用の違いは、百歩譲って、あってもいい。ただし、ルールは競技者・審判・観客(見るもの)の三者が共有して初めて機能するもの。「なんとなく」ではなく、意図・目的・基準を明確に宣言したのちに意図的に行われることが絶対条件。
・「間違ったものは直せるが、意図のない誤りは直せない」
・「国際大会と国内大会のルール運用の違いが、選手に多大な負担を強いている」ことだけははっきりしている。審判委員会はそろそろこの点だけは、せめてまっすぐ認めるべきだ。
・以降は派生して「審判」の位置づけについて。柔道競技に占める位置づけが、いわば職人集団だけでは仕切れないほど大きくなってしまった。時代の変化がもたらしたこのパワー(権力)に、審判委員会も全日本柔道連盟も無自覚なことが大問題。審判委員会の外に、マネジメントと評価に特化した上部機関を組織するなど、体制から考え直したほうがいい。
テクニカル的には完全な「シロ」、少なくともDHはありえない
物議を醸した、そしてV候補筆頭・東海大敗北の呼び水となった新井道大のダイレクト反則負け。これははっきり言っておきたいが、テクニカル的には全く反則ではない。
スポンサーリンク