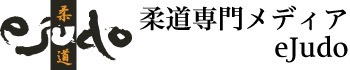文責:古田英毅
Text by Hideki Furuta
早出し評、ということでひとまず4題お送りする。
差し出される「誘惑」を峻拒、神様のテスト乗り越えたチフヴィミアニ戦

髙藤直寿(パーク24)は素晴らしかった。優勝候補の筆頭に挙げられながら金メダルを逃したリオデジャネイロ五輪以来の、この5年間の成長を凝集したような戦いぶりだった。白眉は最大の山場と目された準々決勝、2019年東京世界選手権の覇者ルフミ・チフヴィミアニ(ジョージア)との一番。後の先の得意なチフヴィミアニは、返し技狙いが基本。世界選手権に優勝し、そのストロングポイントが周囲に知られてなお勝ち続けるこの人の持ち味は幾度投げられそうになってもギリギリで耐え続け、相手の「最後の詰め」を引き出すことにある。あと半歩の踏み込み、あとひと間合いの胸の引き寄せ、仕上げの「体の捨て」。柔道家の「投げたい」という抗いがたい本能、ここまで階段を登ってさえおけばあとは絶対に大丈夫という「詰め」の誘惑、これを引き出しては、時には己も吹っ飛ばされながら、ギリギリ畳に背中を着く瞬間に態勢をひっくり返して最後は上になっている。こういう柔道だから掛ける技も投げるためというよりは、「際」を作るのが目標。相手を「その気」にさせる一種甘い、面倒くさい体勢を作るためだけに強く組み、すこしズレた技を掛け続けて、ひたすら「縺れ」を演出し続けたGS延長戦の振る舞いをこの観点で見直してみて欲しい。チフヴィミアニの試合は「もつれさせて返す」という補助線があって初めて読み解けるものなのだ。
しかし髙藤はこの誘惑に一切乗らなかった。本戦ではこの相手に低い担ぎ技に入り込むという最大のタブーを犯して返し矢の隅返一発を食ってしまったが(ノーポイント。今日最大のピンチだった)、以降は攻めつつ、小内刈狙いを軸に色々な方向に角を出して揺さぶりつつ、決してラスト1マイルのデンジャーゾーンにだけは足を踏み入れない。チフヴィミアニは「指導」を押し付けられ、徹底的に封じられ、しかも投げの予感に晒され続けて疲弊。ご存じの通り最後は「ベアハグ」の「指導」で敗れることになるのだが、これはもう、これ以上試合を続けられないと抱き勝負に出ざるを得なかったチフヴィミアニの完敗。髙藤の「詰め将棋」の勝利であった。
打ち続く「投げ」への誘惑。眼前に差し出され続ける「あと一段だけ」先にある頂上。よく考えてもらいたいが、これを晒され続けるのは髙藤なのである。あの2013年、溢れる投げカンと身体能力をテコに異次元の大技を連発、才能と欲求の赴くままの柔道で世界の頂点を極めたあの天才・髙藤なのである。筆者にはこの試合、柔道の神様が「変わった変わったと言うけれど、2013年のお前と、いまのお前は本当に変わったのかい?」と髙藤を試し続けているようにすら思えた。絶対に負けない柔道、何があっても頂点に立つ柔道、力がある限りは絶対に勝つ柔道、髙藤が求め続けたこの境地に、まさに最後の試験が課せられているなと感じた。ここを勝ちぬいた髙藤の優勝は、論理的な帰結であったと思う。髙藤は戦後「相手を知れば知るほど、体が硬くなった」「相手のストロングポイントを知れば知るほど、技を掛けるのが怖かった」と試合を振り返った。なんの、髙藤の勝利の所以は相手を知り、己を知悉するがゆえ、そして「勝つために」適切な行動を選び続ける理性あってのことである。少なくとも、たぶん「地」の力は今より上だった2016年の髙藤では、ビッグゲームでチフヴィミアニに勝つことは絶対出来なかったはずだ。凄み漂う戦いだった。
過去といま、「ふたりの髙藤」が繋がった準決勝

「地」の力はもちろん、髙藤の純粋な「受け」の力(体だけで回避する力)は実は往時より下がり、これは軽量級選手の宿命でもあるのだが、むしろいいところに入られたときに一発飛んでしまうリスクは大きくなっていると思う。さらにGS延長戦の激戦続きで疲弊した準決勝以降は当然ながら本丸(体だけの受け)の周囲を囲む防壁(組み手など)の密度が徐々に甘くなり、もっとも危険な「力比べ」体勢が出来るリスクはさらに上がっていた。
そんな中で、潜り技がベースでしかも突如加速しての一発というジャンプ力を持つイェルドス・スメトフ(カザフスタン)、さらに若くてしかも組み合わせ的に消耗度少なかったヤン・ユンウェイ(台湾)という2人を相手にするのは凄まじく精神に負荷が掛かる仕事のはずだ。スメトフ戦はこの日のベストバウト、投げに、そして寝技にとまさに死力を尽くした戦いだったのだが、辛ければ辛いほど、一発勝負で試合を終わらせてしまいたくなるのが選手の常。前段の準々決勝と被るのだが、この試合でこの一種の思考停止でもある「一発勝負」に絶対に踏み込まなかった髙藤の姿からは、筆者はその駆け引きの上手さや理性の高さよりもむしろ、この5年間髙藤が舐めた辛酸がいかにキツいものであったか、プライド高い髙藤が「勝てなかった人」としてラベルを貼られた屈辱がいかに重いものであったかのほうを、時間いっぱい、強く感じさせられた。髙藤が頑張れば頑張るほど、忍耐強く勝機を待ち続け、勝ちへのシナリオを開かんと我慢をすえればするほど、それを思って切なくなった。だからこのスメトフ戦の出口が、2013年世界初制覇時の天才・髙藤が生み出し、そして世界に広がった「ナオスペ」であったこと(相手の支釣込足を呼び込みながら捩じり返す。今回は相手の膝車を弾き返しながら捩じり返す形になったが、同じものだ)はひときわ感慨深かった。あの2013年世界選手権を爆発的な身体能力と凄まじいセンスで制した怖いものなしの天才・髙藤、「リオ前」モードの自分に「リオ後」の髙藤がアクセスした、過去といまの二人の髙藤が繋がった瞬間だったと思う。感動的なエンディングだった。
満タンのチューブからしか、絞りだせないものがある

というわけで決勝のヤン戦も我慢の柔道を続け、万が一にも勝利を逃さない、一発勝負の土俵に「降りてあげない」我慢の柔道でひたひた勝利に迫った髙藤だが、本人はこれを「わかりにくい、TVで見ていても絶対にわからない柔道」と苦笑してみせ、周囲も「勝ちにこだわった」「勝ち方は地味だが」と評価する。
そんなことはない。とういよりも、「ある」(一見地味な勝利にこだわる勝ち方)のだが、ここで理解してもらいたいのは、この作戦を採って勝つにはそもそも論として圧倒的な実力が必要であること。
髙藤が志向したのは、柔道の強さそれ自体ではない。強さの追求は大前提。求めたのは、圧倒的な力を持つ自分が、100回やって100回優勝するための柔道。たまたま調子が良いときに、「優勝という称号では足りないくらいの圧倒的な勝ち」を収める柔道ではなく、強い限りは調子が悪くても絶対に勝つ、方法論のほうだ。
対人競技でこの方法論を追求する限り、己の目線は他者へ、そして己自身の深い部分に向くしかない。髙藤の(かつてから考えれば)意外なまでの自己理解の深さ、「マニア」とまで呼ばれる映像研究(本人は単に好きなだけと語るが)による他者へのまなざしの深さは、上記の方法論から生まれた、必然だった。
ちょっと話が逸れたが。敢えていかない、だけでは「指導」が来る。我慢を続けるだけではこれも反則が取られる。たとえ練れていても同じ組み手を続けては相手に付け入られる。単なる膠着ではなく、常に相手を揺らして投げの恐怖を感じさせなければ、考える時間と余裕を与えて一段上の逆襲が来る。
そしてこういう手札の開発と選択、実行を許されるためにはそもそも論として圧倒的な強さが必要なのである。十分以上の水圧がなければホースから安定した水流を出すことは出来ないし、満杯のチューブからしか、適切な量の中身は絞りだせない。少ない中身を無理やり絞れば、行き過ぎたり、少なすぎたり、そこにあるのは「大体」、これが生み出すものは「失敗」である。髙藤の「渋い」(本人)勝ち方の裏に圧倒的な実力という裏付けがあることを、ぜひ理解しておいてもらいたい。柔道人は十分理解しているであろう。周囲のファンに、ぜひ伝えて欲しい。
たびたび漏らして来たので筆者の周囲のひとたちは「耳にタコ」かもしれないが、筆者は今回「もし自分が神様で、1個だけ金メダルを誰かに獲らせることが出来るなら、髙藤選手に獲らせたい」と言い続けていた。もちろんどの選手にも獲って欲しいのだが、一敗地にまみれて努力することはもちろん、ここまで己を「変えた」髙藤は、それに値するだけの努力を積み重ねて来たと思うのだ。
頑張ったものが、願いをかなえる姿は素直にとても、いい。髙藤選手の金メダル獲得、5年に渡る苦闘のハッピーエンドを心から祝福したい。
恒例の「全員サイボーグ化」は起こったのか?

第1シード、今回も「五輪におけるロシア勢の確変」を起こすかと思われたロベルト・ムシュヴィドバゼ(ロシア)が初戦敗退。もう、確変どころかボロボロ、動きは重く、息は切れ、2回戦でトルニケ・チャカドア(オランダ)に体幹を捕まえられての内股「技有」に沈んだ。
シャラフディン・ルトフィラエフ(ウズベキスタン)も初戦でアルテム・レシュク(ウクライナ)の巴投を食って「技有」優勢で敗退。世界選手権で3位に入賞したばかりのフランシスコ・ガリーゴス(スペイン)も初戦でルカ・ムヘイゼ(フランス)に己の得意技でもある肩車で「技有」を食って、沈んだ。
一巡目が終わったところで、率直に「凄まじい出来の選手はいないな」と思った。あの、異常なハイコンディションで選手の力が一斉に上がるインフレ現象、「サイボーグ化」は今回は起こらないのか。やはりコロナのせいか、それとも加速装置としての観客がいないせいか。
終わってみれば、やはりこの「サイボーグ化」は起こったのだと思う。上がる人数が多く、これまで以上に一斉にそれが立ち上がったから目に見えにくかったのだろうな、と捉えている。現実として前述のムシュヴィドバゼ、ルトフィラエフ、ガリーゴス、そしてたとえばキム・ウォンジンはこれについていけずに取り残されたわけだし、ヤン、スメトフ、ルカ・ムヘイゼ(フランス)、チャカドア、レシュクらは、もはやこれが当たり前ですよとばかりに引っ張りあがっていた。髙藤は「全体的なコンディションの急上昇についていく」という積年の課題をきっちりクリアし、どころかハイコンディション選手同士の削り合い3戦をすべて生き残って頂点に辿り着いたわけである。
60kg級は調整が難しく、平時のツアーでは有力選手のコンディションが揃うことは稀。年1回の開催となった世界選手権も五輪重視の選手とは価値観がまとまらず、これぞの顔が全員揃うこと自体がそもそも少ない。60kg級にあってこの五輪はまさに唯一無二の大会。髙藤はこの五輪に勝って、真の世界一の座についたのだと思う。
(了)
スポンサーリンク