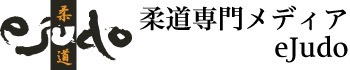文責:古田英毅
Text by Hideki Furuta

60kg級評を書き終わったあとだが、もう1本追加したくなったので独立して書かせて頂く。
試合後のミックスゾーンで、無観客開催について「寂しさはないか」との旨問われた髙藤直寿の言葉が印象的だった。「あのでっかい日本武道館のど真ん中に自分と相手が2人だけで向き合う感覚、相手の息の音が聞こえるくらい、それが良かった。シーンとした中で2人だけで戦って、終わったら相手を称え合う。凄く良い経験になりました。」
これに、今朝がた顔を見るなり私のところまで走って来て熱っぽく語り始めた、同僚(私はリオ大会に引き続き、オリンピックのために招集された公式映像制作チームの一因として活動している)の言葉が被った。国内外を問わず年中世界中を飛び回って試合場の間近でスポーツイベントに携わる彼は、現場でスポーツを「見る」こと、そして「感じる」ことに関してはまさにプロフェッショナルである。その彼が髙藤の準決勝イェルドス・スメトフ戦を見て、異常に感じ入っていた。「何かを感じた」という言葉にならないその言葉を繋いでいくと、「誰もいない静寂の中で、世界のトップレベルの2人が死力を尽くす様にただならぬものを感じた」「この雰囲気は、たとえばサッカーの無観客試合では絶対にない。」「サッカーでは観客がいないと練習試合みたいな雰囲気になる。選手自身もそう言っている」「そういう練習試合っぽさを微塵も感じないどころか、あの2人のことしか見えなくなった」「戦ううちに彼らが人間でない存在になるのを感じた」「これは、選手2人のレベルの高さはもちろん、『武道』だからではないでしょうか」。と。
筆者は彼の感性の高さを是とする。そして「これは武道ならでは、ではないのか」という観点が実に面白い。そもそも武道は人に見せるものではなく、成熟後の武道の「試合」はあくまで己と相手が雌雄を決することで、己が(ひょっとすると相手も)一段上の高みに上らんとするものである。その場は夜陰の道場なのか城郭の奥座敷なのか野っ原なのかわからないが、そこにそもそも、観客の目は想定されていない。試合はあくまで修行の一。「クローズド」に相性が良いもののはずなのだ。柔道が相手との肉体的対話に「やりとり」を依存するものであることも、この「2人だけで向き合う」状況の密度を上げる。無観客の聖性とでも呼ぼうか。増して場所は日本武道館であり、設定は五輪である。日本武道館という神域に、世界一を目指す宿命を負った相手と自分のみが存在し、たった1つの目的のために、互いにすべてを振りそぼって死力を尽くす。同僚が「人ならぬものに上がろうとしている」と一生懸命例えた、その感情の固まりがなんなのかがわかる気がする。特別な時間、特別な場、特別な人間、静寂さと遮蔽性、そして特別な行動(死力を尽くして戦うこと)。こう並べると儀式めく。これはもう、存在としての「次元上昇」の場とすら言っていいのではないか。

髙藤は決勝戦が終わった後、「座礼」をした。「体が勝手に正座して礼をした」そうである。ほぼ無意識にそうなってしまったのだという。囲み取材の場で理由を問われるとちょっと自分の中にあるものを言葉にすることに苦労しながらも、「講道館や、神聖な場では普段から座礼をする」と答えた。これは、髙藤の感性が、遮蔽された相手と自分しか存在しない空間、特別な時間、特別な場所、すぐれて武道的なこの「上昇」の儀式に感応したからではないのだろうか。
というわけで。無観客について多々議論ある中で少々変化球的かもしれないが、「武道」(由来のスポーツ)の無観客は他の競技とは少々違うものがあるのではないか、そして4年にただ1回全員が本気で世界一を目指すという設定と、集った技熟達に至った修行者たち、日本武道館という「聖具」を得て、この側面がより強くわかりやすく見えてくるのではないか、この先の7日間も昨日のような素晴らしい試合、「上り詰める」戦いが見られるのではないか。こんな期待を持ってしまう。
大会が終わると「ちょっと思い入れ過ぎだ」「実際そうはならなかった」となってしまうかもしれないので、初日の素晴らしい試合の興奮冷めやらぬこの段階で、1度アウトプットさせて頂く。今日も熱戦に、大期待だ。
(了)
スポンサーリンク