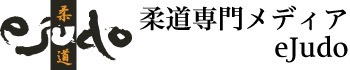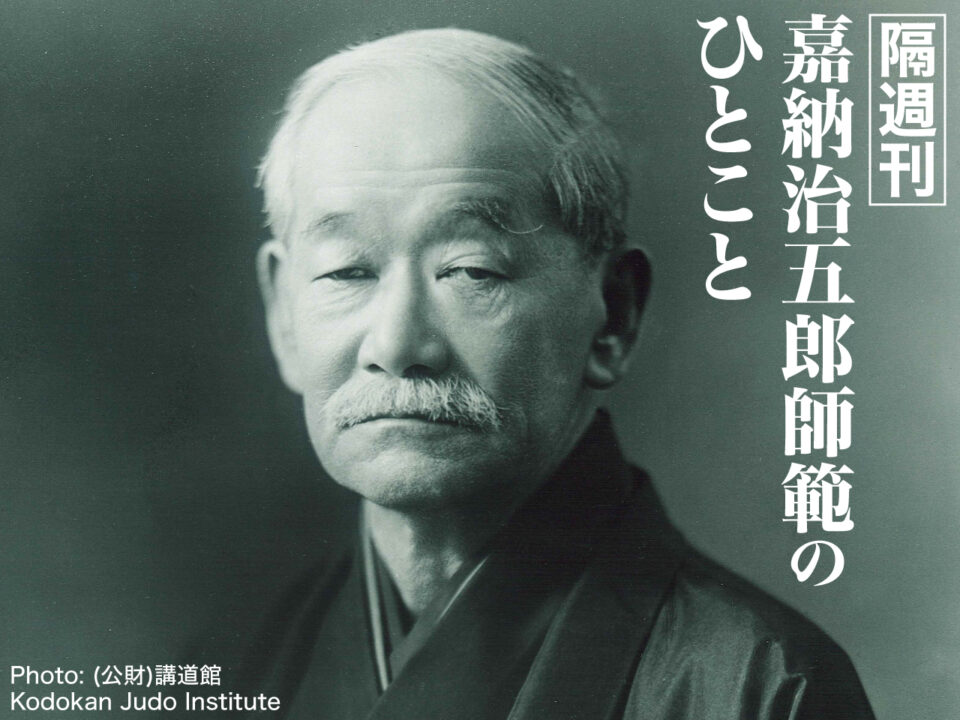
「審判は神聖なるものとしてあるのであるから、仮に審判員の判断に過失があっても、審判自身が取り消さぬ以上は、一度宣告した決定は、動かすことの出来ぬものとなっている」
出典:「福岡県における東西対抗大試合に出場する選士および審判員に対する予の希望」柔道7巻5号 昭和11年(1936)5月 (『嘉納治五郎大系』2巻395頁)
本連載の第5回で、師範の試合観を紹介しましたが、今回は、試合には欠かせない審判について紹介します。
今回の「ひとこと」を一読した読者の皆さんから、「審判が間違っていた時は、どうするんだ!」という声が聞こえてきそうですね。
<審判も人間である以上、間違いを犯すことがある>ということを前提として、三審制(本来審判は1人で行うものでした)やケアシステムは成立しています。
師範も審判員が必ず正しい判断をすると思っていなかったことは、冒頭の言葉から分かるでしょう。ただ、間違った判定をしたとしても、審判員本人以外は、その判定を動かせない(=変更できない)としています。別の史料では、審判員が間違った判断をしても、試合者は不幸だったと思って諦め、その判定を受け入れるように言っています<原文:「自分の不幸と諦めあくまでも審判者の判定を重んじなければならぬ」>。今の感覚からすると受け入れがたい発言です。審判の「神聖さ」が、その根拠となっていますが、理由はそれだけでしょうか・・・。
私自身の推測というよりも想像に近い意見はあるのですが、その前に、130年を超える講道館の歴史で僅か15名しかいない「十段」おふたりの審判に関するエピソードを紹介したいと思います。
まず、嘉納師範に「愚直」と評された高弟の1人、飯塚国三郎十段。その審判ぶりは身内に甘く他者に辛いところがあり、これでは飯塚門下と試合をしても勝てないと師範に直訴した人がいたと伝えられています
次に「空気投」で知られ、歴代十段の中でも「名人」という称号がふさわしい三舩久蔵十段。あろうことか、全日本選手権の決勝戦で技が決まったところを見て見ぬふりをしたという話を当事者である故猪熊功先生が遺しています。ただ、猪熊先生によると、そのようなことは三舩先生に限らず当時はよくあることだったようです。
現在からすると少し考えられないような例を取り上げましたが、師範から直接、薫陶を受け、十段に到達した人たちでも、このような話がある中(猪熊先生のお話は戦後の話ですが)、師範は審判を神聖とし、その判定を受け入れることを促したわけです。なぜ、このようなことを嘉納師範は言ったのか。ここから先は、筆者の推測ですが、その理由は2つあると思います。
これまで紹介してきた「ひとこと」を含む他の史料からも分かりますように、師範にとって試合は柔道の目的ではなく、目的に達するための手段の1つでした。もちろん、試合の結果に過ぎない勝敗については言うまでもないでしょう。
あくまでも、修行の一手段にすぎない試合においては、その勝敗について、とやかく言うことよりも理不尽と思われる判定でも、それを受け入れ修行の糧とすることを重視したのではないでしょうか(そのことを象徴的に表す言葉が「順道制勝」ですが、「負けても道に順って負ければ、道に背いて勝ったより価値があるのである」とまで言い切っています)。
社会には理不尽なことが数多くあります。ですが、それらの理不尽に屈することなく耐え忍び、後日の再戦を期す気概が必要とされるのは皆さんもご承知の通りです。目前の勝敗にこだわるのではなく、将来の糧にする。そのため、あえてこのようなことを言ったのではないかと想像しています。
もう1つは「教育の場として試合」という面からですが、こちらについては、次回以降、別の「ひとこと」と絡めて紹介したいと思います。
最後に。師範は「神聖性」を主張する一方で「(過った審判をした場合)他人から非難を受け、信用を失墜することは免れ得ないのである。それゆえ審判員たるものはあらかじめ審判規則を精密に研究しておき、また心力を傾倒して、規則の適用を誤らぬよう留意を要する」と審判員に釘をさすことも忘れてはいません。
※読みやすさを考慮して引用は『嘉納治五郎大系』から行っています。
著者:元 敏季(ハジメ・トシキ)
1975年生まれ。柔道は中学校から始め、大学までは競技を中心に行うが、卒業論文を機に柔道の文化的側面に関心を持ち、大学院へ進学。凡そ10年、大学院・研究機関に所属するも、研究とは異なる分野の仕事に就き現在に至る。ライフワークとして嘉納治五郎に関する史料を蒐集・研究し、その成果を柔道振興のため発信しようとしている。
スポンサーリンク