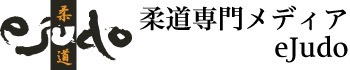文責:古田英毅
Text by Hideki Furuta

日本代表の田代未来は既報の通り2回戦敗退。ワールドランキング21位のアガタ・オズドバ=ブラフ(ポーランド)の左小内巻込「一本」に沈んだ。
リオ五輪に続いてメダルなし。大会前、少なくとも2020年の五輪延期時点ではクラリス・アグベニュー(フランス)とティナ・トルステニャク(スロベニア)に並ぶ「3強」、どころか相性を考えればもはやアグベニュー以外に敵はいないと目されていた田代だが、まったく意外な結果となってしまった。この5年間の来し方を考えるに、あまりにも酷な結末。アグベニューとトルステニャクの決勝と、試合後のあの抱擁を田代はいったいどのような気持ちで見守ったのだろうか。切なくて、胸が痛くて、想像することすら憚られる。出来れば、触りたくない。
それでも、理由は探さねばならない。これだけの番狂わせだ。実相はどうあれ、思考を巡らせないわけにはいかない。
当日直感的には、田代はやはりアグベニュー対策に自信がなかったのではないか、その不安や拭い難い忌避感が一種体の方に「負け」を選ばせてしまったのではないか(本当にアグベニュー対策が完了していて自信があったのなら団体戦決勝は田代投入があってもよかったはずだ)と感じたのだが、これはただの印象で外側からの検証は不可能。わざわざ人前で語るようなレベルのものではない。また、リアルタイム観戦時はオズドバ=ブラフ唯一の必殺技左小内巻込に対する警戒が甘いように見えたことから対戦相手に対する研究不足を疑ったのだが、映像を見返すと(当日すぐに試みた)田代はこちらの印象以上にこの片手技を封じるべく両手で持つ行動に出ていたし、戦後は自ら「あの技が来ることはわかっていた」とも語っている。なぜあの時の進退があんなに危ういと見えたのか(なぜか物凄く「掛かりそう」に見えた)についてはもう1度技術的な観点から思考を巡らせるべきだが、研究不足自体を敗因として推すには当たらないだろう。
それでも敢えて理由を探すのであれば。「点」ではなく「線」で見るしかない。田代は、女子63kg級にこの5年間絶えてなかった、そしてついにやって来た中堅層全体の押し上げに飲み込まれたのだという見方は出来る。筆者はまず、これを採る。
最後の最後にやってきた、63kg級中堅層の「上げ潮」

女子52kg級と同様、この階級は長い間、中堅以下の選手の突き上げがまったくと言っていいほどなかった。冒頭書かせて頂いた「3強」構図は実はリオ五輪の時に既にほぼ完成していて、かつ以後の5年間、ここに迫る勢力はゼロ。以降の層は多少の攪拌あれど「跳ねる」選手は現れず(日本人選手を除く)、3強の足元に迫るような選手など、まさに誰一人いなかった。
限られたトップ選手以外の中堅以下が極端に停滞するというこの構図は、63kg級に限らずこのリオー東京期の特に前半戦、いくつかの階級に見られた。男子66kg級や前述の女子52kg級、ちょっと趣が違うが女子70kg級などがそうだ。その中で、男子66kg級は2019年から急激に人材が勃興してあっという間に屈指の激戦階級に変貌したし、時をほぼ同じくしして女子70kg級も中堅層が上位と競り合い始めて一気に混戦模様となり、52kg級も五輪延期を経た2021年になってからチェルシー・ジャイルス(イギリス)らを筆頭に中堅層が塊となって序列の梯子を上り、トップ3に迫った。全体のレベルは急激に上がった。
そして最後の最後まで残っていた63kg級も、実はギリギリでこの現象が起こっていたのではないか。ブダペスト世界選手権で鍋倉那美を破ったアンリケリス・バリオス(ベネズエラ)は長い手足を生かした組み手と伸びのある技でこの五輪も堂々上位と渡り合って3位決定戦まで進んだし(その自己理解が利いた進退と理のある柔道、上位対戦で平然と呼吸する試合態度を見ると、鍋倉撃破が決してフロックでなかったことがよくわかる)、5月のグランドスラム・カザンを得意の左小内巻込一本槍で優勝したオズドバ=ブラフはこの階級に絶えて現れなかった「跳ねた」選手である。ブダペスト世界選手権で決勝まで進んだアンドレヤ・レスキ(スロベニア)の活躍も中堅層からついに大きく跳ねたと確信させられたし、五輪本番ではベテランのキャサリン・ブーシェミン=ピナード(カナダ)や、マリア・セントラッキオ(イタリア)の活躍も予想以上。ブダペスト世界選手権の逞しい戦いぶりで復活を印象付けたケトレイン・クアドロス(ブラジル)は今回も良かったし、五輪の大舞台でマルティナ・トライドス(ドイツ)に大外落「一本」で引導を渡したオズバス ・ソフィ(ハンガリー)はなかなかニューカマー現れぬこの階級に新たな時代の到来を感じさせた。なにより、どの大会を見ても面白味に欠けたこの階級の予選ラウンドが、この五輪は、びっくりするくらい面白かった。63kg級の国際大会で、試合自体がこれほど面白かった大会はこの5年ちょっと覚えがない。明らかなレベルアップ。中堅層が上げ潮に乗っていた。
変われなかった田代

五輪直前にやってきた、津波のような中堅層の押し上げ。その中にあって、トップ選手たちはいかにこれを凌いで、その上を行ったのか。キーワードは「進化(変化)」だと思っている。52kg級の絶対王者・阿部詩を最後に救ったのはかつてほぼまったく出来なかった寝技の強化と、ギリギリまで探り続けた戦型(組み手)のオプション増加だったし、70kg級の新井千鶴は最後まで大会に出続けて組み手の試行錯誤を止めなかった。66kg級の阿部一二三は苦手のケンカ四つに技・組み手とついに明らかな解を見出し、ギリギリまで足技のオプションも増やし続けた。
そしてこの63kg級にあって、リオ五輪時からもっとも柔道を進化させたのはアグベニューである。新たに持ち込んだ「ネクタイチョーク」や左小内刈(頻度も練度も各段に増した)はいまやもっとも取り味のある必殺技。組み手もさらに練れて、腕挫十字固や「腰絞め」など一瞬で決まる固技技術も立ち技とシームレスに繰り出してくる。かつてアグベニューの柔道に濃かったギャンブル性が薄れたのは、これらの手札の増加が採れる作戦の幅を押し広げたからである。右組み左一本背負投という変則の機関車攻撃一本槍でリオ五輪を採ったトルステニャクも、このままでは限界ありとばかりに一時は左右の内股という意外な方向に舵を切ってまで、自分の柔道の「器」自体を押し広げんとしていた。結果としてモノにならなかったものもたくさんあるのだが、あの挑戦の時期なくして今のトルステニャクの強さは語れない。採れる戦型と登攀ルートが増え、結果として得意の左一本背負投が決まる率も上がった。具体的に今回の準々決勝では、バリオスと「技有」を取り合ってタイスコアという綱渡りのGS延長戦を、左一本背負投フェイントの変則谷落という新技に命を救われ、合技「一本」で勝ち上がっている。

一方、田代はここまで劇的に柔道を変えることはなかった。少なくともこの3人の中では、もっとも変わっていない。端的なのはコロナ後唯一の出場となった3月のグランドスラム・タシケント。アグベニューとトルステニャクが出ずライバル皆無のこの大会で、田代は厳しい組み手と手堅い試合運びで、引っ掛かりゼロのまま圧勝Vを飾っている。他の日本代表選手が新たな挑戦を試みる中、はたまた久々の試合で試合勘戻らぬ己の戦いぶりに戸惑いながら目の前の藪を漕いで「課題」を得る中、田代はこの大会を現状の力と技術で圧勝することを選んでこれを完遂した。五輪までの1年半で唯一の出場となったこの機会を、現在の力と立ち位置の確認に費やしたと言っていい。
田代は、そうするしかなかったのかもしれない。この時点、この面子(決勝のアンドレヤ・レスキ以外に試合になるレベルの相手はおらず、そのレスキも五輪代表は絶望的だった)では田代がきちんと試合をしたら圧勝してしまう。苦しい場面すらなかなか訪れない。よほど強く意識しなければ、新しいことを試すことは難しかったろう。
そしてまた、そもそも田代がいったいどの方向に角を出して新しいことを伸ばすべきか、これを見出すことが難しいハイアベレージ選手であったという本質的な問題もある。組み手、投げ、足技、寝技、そして今回の女子日本代表の共通課題であった「立ち→寝」、そもそも田代はこれらすべての平均値が高く、尖りも凹みも極端に少ない。このあたりは少年柔道最加熱期の産であり、当時の少年柔道文化の結実と言える田代の柔道の、実はもっとも難しい部分だ。相原中時代の田代は、力、組み手、投げ、寝技と、たぶん当時の少年指導者が「こうあるべき」と考える方法論の、理想的な体現者だった。たとえば内股の手練れ(時折現れる業師タイプ)が見せる異常な投げカンや隔絶したセンスなどの「尖り」を感じさせることはなかったが、それによって生まれる「歪み」や脆さもまたなく、勝ちぶりの派手さと手堅さを両立させていた。体がそもそも強く、しっかりした組み手と足技で崩し、威力のある技で投げ切って「一本」を取り、果たせぬとなれば寝技で仕留めてキッチリ結果を残す。どの項目も常人では1つたりとも辿り着くことすら難しいハイアベレージで並べているのだが、キャリア通じて極端な「尖り」を見せることもまたなかった(ただし淑徳高時代は「投げ」に尖りを見せた時期があったと思う)。あの時期のメソッド柔道の申し子であり、最高傑作であったと言っていい。田代に限らずこういう破綻のない選手は、どちらに角を出して伸びていくべきか、次の方向を見出すのが非常に難しい。しかも田代は方向性を変えず己の身体と柔道をブラッシュアップしていくという方針のまま、アグベニュー以外には全員圧勝するという世界屈指のレベルまで強くなってしまった。かつ、追走するライバルたちが集団で停滞。この中では、己のフレームを突き破るような柔道の改造を考えるのはやはり難しい。
そうであっても。今回の結果から言えば、それでも、無理やりにでも、たとえ歪になってでも、新しいことに挑戦して柔道の幅を広げねばならなかったと考えるしかない。そもそもアグベニューに勝っていない中での方向性の堅持が大戦略として是であったのかどうかという点に疑問を持たねばならない。隔絶した力を持ってしまった以上は、無理やりにでも成長を求めていくしかなかったはずなのだ。
今回の敗戦には、海外の中堅があまりに停滞したゆえ、この期間「跳ねた」選手を力づくで鎮めた経験がなかったことも痛かったと思うのだが、こういう「出来ない経験」を埋めるものも、無理やりにでも期する成長、歪になってでも求めねばならない変化だったのだと思う。
敗者としてこの5年間をスタートしたアグベニューが絶対王者の座に就きながら常に進化し続けて己のフレームを押し広げた様、あるいは男子100kg超級のテディ・リネールが新たなルールと重量級生態系の変化に対応するためまったく試合ぶりを変えた姿、あるいは他と隔絶した強さを持ちながら確実に毎年使える技を増やしてきた73kg級の絶対王者大野将平の研鑽。そこには「成長し続けなければ勝てない」という勝負ごとそのものに対する理解と、無理やりにでも成長の方向を見出さねばならない、そのために脳漿絞らねばならないという切迫感があった。実際に彼らの柔道は、日々少しづつ変わり続けている。
少年柔道最加熱期のメソッド柔道の最高傑作、多くの先駆者の思考の結晶を早い段階で体に仕込まれた田代に足りなかったのは、実はこの部分だったのだと思う。あの2019年世界選手権決勝の熱戦後、勝ったアグベニューは以後の2年間それでも成長を止めず、新たな技術を盛り、手札を増やして少しずつ己の柔道の枠を広げ続けた。一方敗れた田代はもっかのスタイルをブラッシュアップすることにリソースを注いだ。成長への視座、柔道の枠を考える力の部分での敗北である。自身の枠内での最適解を探すことには長けていたが、枠自体を広げるための方法論を持てなかった。
このあたり、大きく言えば田代が強すぎるハイアベレージ選手であったからこそ見逃されてしまった部分とも言える。田代は進化するための方法論を持てず、相手の想定以上に進化しなければかわせない、急激な追撃勢力の押し上げに飲み込まれた。筆者としては今回の敗戦をこう捉えている。進化を止めなかったアグベニューとトルステニャクは残り、柔道を変えられなかった田代(ともう1人、トライドスの名前を挙げておきたい)は飲み込まれた。そういう大会だったのだと解釈する。
「変化」「進化」をキーワードに問題の場面に立ち戻る
そして最後にもう一項。ここまで書いて考えた上で、冒頭挙げたシーン。なぜだか危うさを感じてしまったオズドバ=ブラフ戦の進退について、「進化」「変化」と絡ませて少し考えてみたい。
左小内巻込(片手技)封じのために田代は両襟を持ったのだが、田代もともとの柔道に両襟オプションの印象は薄い。再度試合を見返すと、田代は確かに確信的に両襟を持って、この間オズドバ=ブラフはまったく技を出せていないのだが、田代の側もかなりやりにくそうでほとんど攻め手がない。そのままでは攻めにくいので自ら離して片手状態からやり直すことを幾度か続けるが、さすがにこれは危険と判断したか次のシークエンスではもう1度徹底的に両襟を持つ。そうするとやはり自分が攻められず、掴み続けたまま結局は「待て」で試合が止まる。そして続く展開では、いったん襟を掴んだ引き手を早い段階で自ら離し、袖(田代の好きな形だが切られやすい)に持ち替えてしまう。惨劇が起こったのはこの直後だった。オズドバ=ブラフが容易に切り、片手状態からの左小内巻込一撃「一本」。やるべきこと(両襟)はわかっていたが、出来ること(手札)とのバランスが取れなかったと捉えるべきだろう。片手技封じ(あるいは格下潰し)のオプションをしっかり確立して、両襟を持ったまま攻め続けていればおそらくオズドバ=ブラフは何も出来なかったはず。守りの形(両襟)と、攻めの形(引き手で袖)が分離していた。この手の選手と戦うための戦型をオプションとして持てていなかった。やはり、変化・進化に対する貪欲さの不足は、直接的にもこの敗戦に影響していたと考える。
変化し続けることが難しい環境にいた田代。しかし勝ったアグベニューは、それ以上に難しい環境にいながら、変わり続けることを厭わなかった。どう変化するかを、脳漿絞って考え続けた。そして神は、相手がいないほど強くなっても、課題を見つけ難いほど勝ち続けても、それでもなお進化し続けようとする2人(アグベニューとトルステニャク)に祝福を与えた。「中堅層の押し上げ」に加えて、63kg級に加えるべきもう1つの観察はこれだと思う。
失礼なことを言っているかもしれない。また、リオ五輪後の田代の姿、そしてなにより、揚がる勢いにあった高校2年夏の金鷲旗での残酷な膝の負傷、そしてあの絶望的な怪我からの復活を思い出すに今回の敗戦は本当に切ない。まことに筆が重かったが、この敗戦に思考を巡らせないのは逆に失礼と思い1本書かせて頂いた。何卒ご理解を願いたい。
スポンサーリンク