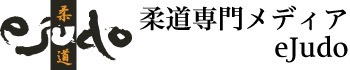文責:古田英毅
Text by Hideki Furuta

阿部詩は準決勝からギアを上げた。序盤戦は手数に振ってどこか腰高の試合を繰り広げていた阿部が、準決勝からピタリとモードを変えた。組み手厳しく進退に隙がなくなり、必要なタイミングで的確に加速し、最小限のリスクで取りに掛かる。だがここから先、我々は「すべての選手に狙われる」立場で迎える五輪の難しさを知ることになる。準決勝の相手は階級屈指の勝負師オデット・ジュッフリダ(イタリア)。この選手がまず阿部の攻めの起動スイッチになる釣り手の持ちどころを呉れない。持ったときには、引き手を持たせない。2つの手の組み合わせが平均値以上にあがることがほとんどない。もともと粘戦担ぎ技ファイター出身のジュッフリダはこういう泥沼展開は得手、担ぎ技に潰れて手数で先行する。阿部にとって相手が「投げさせてくれない」「持たせてくれない」「手数を取りに掛け潰れられる」ことは織り込み済み、阿部がここに持ち込む対抗策は掛け潰れた潰れた相手の右腕を抱えての「腕緘返し」。東京世界選手権準決勝、かつての絶対王者、あの階級ナンバーワンのパワーファイターであるマイリンダ・ケルメンディ(コソボ)をゴリゴリ、無理やり取り切った、阿部がこの数年新たに積んだ「寝技」という新たなモードを象徴する手札である。

だが、これがまったく出来ない。ジュッフリダは掛け終わると中途半端な決めへの希望を持たず、右肘をぴったり閉まって一切腕を入れる隙間を見せない。予選ラウンドでも相手はこの技を警戒していたが、ここまで露骨に見せたのはジュッフリダが初めて。「阿部が持てず、ジュッフリダが掛け潰れ、しかし腕緘には繋げずジュッフリダの攻勢のまま攻防が終わる」絵が繰り返される。阿部は腕緘が警戒されることは予想済み、肘をしまわれたまま「腹包み」に移る策をきちんと用意していたが、これもジュッフリダは想定内とばかりに、畳と体の間に手を差し入れる隙間を作らない。「腹包み」は大きく言って初動で先行することが前提の技術で、わかっていても無理やり取り切れるような力業ではない。ここまで読まれてしまうと無力。本来であればここで腕緘のターゲットである右腕を「出さざるを得ない」撒き餌の技術を繰り出すべきだが、阿部の寝技にはまだそこまでの練り込みはない。もしくはべったり畳に張り付くその態勢を利用する第三の技があるべきだが、そこまでの準備は、どうやらない。掛け潰れに対する持ち札がもはや尽きたと感じた。マトにする選手の研究と、マトにされる側が持ち込む新たな手札のイタチごっこ。今回どうやら阿部は、研究の上を行けていない。
この試合はGS3分11秒、地力と投げカンを生かした形の右内股「技有」で勝ち抜けたが、試合内容は硬直気味。我々は逆説的に、阿部がかつて己の柔道に「寝技」を持ち込んだことがいかに的確な上積みであったのか、いかにこの「寝技」の存在が阿部の柔道の巡りを良くしていたかを、思い知らされることとなった。

決勝はさらに厳しい戦い。ブシャーは組み手厳しく阿部に持ちどころを与えず、膝つき大内刈、小内巻込に肩車と片手から仕掛けられる「潜り技」を仕掛けてくる。準決勝までを見る限り技の威力とシナリオ分岐の豊かさ(投げる方向を変える決めの多さ)はいずれも嵌れば一発で勝利を決められるレベルだ。しかも阿部が得意な「腕緘返し」と、次なる手段である「腹包み」はやはり想定内。蓋をする、あるいは早々に立ち上がると決めて掛かり、決定的な形を作らせない。
構図だけで言えば。片手からでも「一本」を狙えるブシャー、両袖・片襟・背中と攻撃の組み手を多数持つが2本揃わないと技が仕掛けられない阿部。そして先に掛けられるブシャー、先に掛けられても抑止力となる返し技や寝技の具体的手段を持たない阿部ということになる。つまりは「掛けられ続け、そのうちいつか決定的な一撃がやってくる」という絵だ。これは厳しい。設計図の段階で不利。少なくとも寝技でもう1つ先を行く技術を開発してくるべきだった、世界選手権2連覇者の立場ですべての選手を迎え撃たねばならない五輪の難度は半端ではない、と唇を噛みながら試合の行く末を見守った。しかし阿部はそれでも時折引き手を先んじて抑え、大外刈、内股、打点の高い一本背負投と仕掛けて試合を動かす。通常「構図負け」している試合ではこういう攻撃は刹那的で可能性をあまり感じさせられないものだが、阿部の攻めにはどこか、「これで決められるのではないか」という香りが漂う。反対に大枠優位に試合を進めているはずのブシャーの顔色は、意外にも冴えない。
そして結果から言うと阿部は勝った。皆さんご存じの通り、GS延長戦4分27秒崩袈裟固「一本」。オリンピック初出場、見事金メダル獲得である。なぜ阿部は勝ったのか。「地力」「忍耐」「勝負勘」それはもちろんすべてあたりだが、これらすべてを大前提としてもう少しだけ、この「構図負け」にも関わらずなぜ阿部が勝利したかを考えてみたい。

やはり、ここ数年粛々増やして来た手札が阿部を救ったということだと思う。1つは寝技。本人がかつて勝てなかった角田夏実を追いかける過程で強く意識し、また増地ジャパンが代表選手全員の共通課題として課した寝技が、最後も阿部を救った。ブシャーの集中が切れたGS延長戦、左側を狙って来た肩車を潰すと、膝をついて耐えたその首を右腕で抱え、中腰に固定したまま左で銅を抱えて遠い襟を掴む。自らはほぼ立ったまま。立ち姿勢から繰り出す「腹包み」だ。まだ防御が出来上がる前、互いに寝勝負という意識が出来上がる前にスタートする練れたエントリー。そのまま「フナクボ」に固められたブシャーは動けず「一本」、これで勝負が決まった。
このエントリー、前段書いた「初動で相手の先を行く」という「腹包み」の鉄則を満たしたものであり、同時に「立ち→寝」どころか、「立ち→寝→立ち(ブシャーは立ち上がって逃れようとした)に打ち込んだ。これも増地体制が代表全員の必須課題として挙げていた「立ち技と寝技のシームレスな連携」を体現するものだ。相手が「腕緘返し」に「早々に立って『待て』を貰う」という解で戦っていたその隙をしっかり突くものでもあったところも、戦術眼として素晴らしい。反復繰り返しにより、崩れた形(立ち際)にこれを決められるところまで高まっていた練度の高さも光った。「腹包み」そのものは読まれていたが、技法自体ではなく練度とタイミング、応用力の高さで相手の上を行った形となった。

このブシャー戦に関してはもうひとつ、阿部の「奥襟を叩き返して“組み合う”」という、かつては持っていなかったオプションが生きた。ブシャーはこの試合、右相四つの阿部に対してがっぷり奥襟を叩いて来た。肩車ファイターで釣り手は前襟、あるいは上腕が住処であるブシャーとしては少々意外な挙。筆者はツアーを観察する限りそもそも純粋な強さでももうブシャーのほうが上ではないかという見立てを持っていた(そしていまでもそれは決して的外れな観察ではなかったと思っている)。その強者にがっぷり奥襟を叩かれることはかなりのプレッシャーだったはずだが、阿部は嫌わずに奥襟を叩き返し、敢えて相手の釣り手を切り離さず、持ち合ったまま進退した。これが良かった。おそらくブシャーは、両袖、片襟、背中、そして「一方的な奥襟」が生息域である(そして守備があまり得意ではない)阿部がこの形を嫌って切り離してくるところに潜り技の罠を張っていたはずなのだが、阿部がことごとく組み合ったまま応じるために最後までこの起動スイッチが押せなかった(※具体的な例として、前回対戦した2020年グランドスラム・デュッセルドルフを挙げたい。ファーストアタックでブシャーが奥襟を叩き、窮した阿部は絞り落としに掛かってそのまま首を抜いてしまっている)。阿部に勝利したグランドスラム大阪、そして互いに本気を出さぬことを無言で合意していたグランドスラム・デュッセルドルフの確信的で落ち着いた様子と比べてブシャーの進退にどこか戸惑った様子があったのは、この2つの大会と違って、目論見通りに作戦が進んでいなかったからだろう。
これも、強化サイドと阿部が今年話し合って設定したという「組み手のオプションを増やす」という取り組みが生きたものと思う。阿部は今年出場した2大会でこの課題に取り組み、時には膠着してしまうことがあっても、敢えて前襟を持って「組み合って」進退する場面を作っていた。相手の釣り手を絞り落とすことないまま奥襟を「叩き合う」のも今年から、確信的に持ち込んだのはグランドスラム・カザンのアンドレア・キトゥ戦あたりからだったと思う。筆者は前襟持ち合いに関しては「攻撃が利かなくなる。取り扱い注意」と警鐘を鳴らしていたのだが少々浅はかだった。「棲める」形が増えるということはそれ自体が武器(というよりも特定の形にしか棲めないと相手に付け入られる)である。ブシャーが想定していたそれよりも、阿部の生息域は広かった。嫌わせる、生息域の際を渡り歩かせることで隙を見つける、という前提が崩れたブシャーの攻撃は類型化し(ブシャーのような選手はもっかの目論見が上手く行っているかどうかに、立ち振る舞いの隅々までが左右される)、徐々に動きが悪くなり、集中が切れ始め、阿部に前述「立ち→寝→立ち」の寝技エントリーを許した。成長を止めずに常に課題を探し続ける、「なんでもできる選手になりたい」(本人談)という阿部のこの数年を規定して来たもっとも良い部分、その積み上げが最後に生きた形だと思う。
レポートでも少し書かせて頂いたが。女子52kg級はリオ五輪以降完全な二極分解状態にあり、一部の超強豪選手と「その他大勢」の差があり過ぎる、率直に言って面白みに欠ける階級であった。しかし五輪を前にした2020年春ごろから中堅層が大躍進。津波のように、固まりとなってひたひた上位選手に迫って来た。今回はマイリンダ・ケルメンディとナタリア・クズティナがまさにこの枠の選手2人に食われてついに完全な世代交代が起こったわけだが(まだ残り火のあったロンドンーリオ期の52kg級「パワーの時代」は今大会で完全に終わった)、もし阿部が成長を止めていたら間違いなく食われていたと思う。阿部と同じ2018年と2019年の世界選手権を制して48kg級の絶対王者として君臨したダリア・ビロディドが柔道をまったくアップデート出来ず、彼女をターゲットと定めて徹底的に戦略を練った渡名喜風南に敗れてしまったように。阿部勝利の最大の因は、あくまで成長を止めず柔道をアップデートし続ける姿勢、ちょっと20歳の選手としては出来過ぎなくらいの意識の高さであると思う。
余談ながら。常々思っていたが、阿部の特徴である「腕の長さ」がかなり効いていた。阿部は腕の長い選手で他の52kg級選手とは間合いも、力の伝わり方も異なる。今回ブシャーが見せた必殺の肩車は、どれも意外なほどに可能性を感じさせなかった。阿部の捌きの巧さはもちろんだが、その前提にこのリーチの長さがあると思う。ブシャーは間合いが噛み合わずに、妙な表情をしていた。この身体的記号に注目してもう1度阿部の柔道を腑分けしてみようという気にさせられた。

そして。つらつら書いてきたが、この日の戦いに貼るべきもっとも大きなラベルは「粘り勝ち」ということだろう。実はこの原稿は中盤までが当日書いたもの。以降は大会終了直後に続きを書いているのだが、大きく見て大会序盤3日(+81kg級の永瀬貴規)のテーマは、「我慢」。上手く言えないのだが「勝負ステージ出現の条件として、求められる我慢と消耗」とでも言おうか。まるでもともとシナリオが設定されているゲームのように、決められた時間、定められた以上の消耗ラインまで戦い抜き、我慢し、耐え、このステージをクリアすると初めて勝負を決められる空間がやってくる。阿部詩の戦いは、男子60kg級の髙藤直寿から始まったこの傾向、「今大会の勝ち方」をさらに強く日本代表に示してくれたものだった。構図負けにも関わらず思い切った技で度々「投げるか投げられるか」のチャンスを作って試合を進め、危険な小内巻込や肩車を凌ぎ切ってステージクリア。そして見えて来た勝負空間、ここでついに難敵・ブシャーが見せた隙に的確に刃を入れた。今回のテーマである「我慢」、ここを乗り切り、持ち前の勝負勘と、この5年で上積みした新たな手札を駆使して勝ち切った。初出場の20歳とは思えぬほどの完成度。まさに集大成の戦いぶりであった。
スポンサーリンク