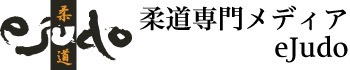文責:古田英毅
Text by Hideki Furuta
「本質」に全振り、最大の長所である自己理解の深さがウルフを救った

ウルフの柔道は素晴らしかった。1年半ぶりの試合となった4月の2大会で抱かされたこちらの危惧や心配など既に先回り。コンディション、戦略、戦術、判断、そして遂行。完璧だったと言っていいのではないか。
わずか1分21秒、足元に火薬でも埋まっていたのではないかという勢いでムハマドカリム・フラモフ(ウズベキスタン)を引っこ抜いた横分「一本」(凄いものを見た)で、まず肉体的条件が出来あがっていることはよくわかった。そして序盤戦のウルフの姿に「いける」と思わされたのは、極力片足を上げずに重心低く二本足で進退しようという大方針が見えたこと。端的に現象を言えば明らかに内股を抑制していたこと、そして得意の大内刈を縦(あるいは斜め)に刈り上げるのではなく、刈り足を接地させて「刈り開く」形を多用していたこと。もちろん構え自体も膝が適度に曲がって腰が沈み、ウルフ本来の、足裏を畳に刷り込むような柔道への志向が明らかだった。これが、良かった。実にわかっていると思った。理由は大きく2つ。1つは、これが「受け」という今回もっとも大きな不安視された課題への適切な解であること。もう1つは、この地を擦るような進退こそ、ウルフの柔道の本質だと思うからだ。
「受け」という眼前の課題が、ウルフをその本質に誘った

2019年4月の全日本選手権の優勝以後、ウルフの柔道の最大の不安は「受け」だった。重心低く進退して相手の技を弾き返すあの安定感が、減量を伴う100kg級ではなかなか発揮されない。同9月の東京世界選手権では苦手のチョ・グハン(韓国)の左一本背負投に崩され続け、最後は投げられてV逸。感覚が狂っていた。同年12月の右膝手術を経てこの感覚のズレは単なる「重さ」のみならず「動き」そのもののズレに繋がり、「動き」のズレはボディバランスの狂いを生んだ。復帰戦となった今年4月のグランドスラム・アンタルヤとアジア・オセアニア選手権ではそれぞれ2位・優勝も、無名選手も含めて大外返、袖釣込腰、小外掛と実に3度も投げられた。お尻が小さくなり、下半身のシルエットが細い。あの膝を曲げて畳に沈み込む、どっしりとした進退が出来ていない。当然無意識的に腰高。それでも本人はつい往時の感覚で受けてしまうので、予想を超えて吹っ飛んでしまう。本番3か月前の状況としては相当な危機である。ただし本人も「小学生時代からこっち、こんなに何度も投げられたことは記憶にない」と呻いたというこの体験、2大会9試合にわたったこの試験運転が、結果的には良かった。本人と鈴木桂治コーチが以後の期間の課題を「受けの確認」と明確に規定(両者ともインタビューで語っている)出来たからだ。もっとも弱い部分の強化に過たずリソースを投下出来た。万が一この受けの狂いが単に感覚的なものでなく膝の故障(両大会ではここぞでうまく曲がっていないように見えた)による物理的要因、あるいはこの間1年の肉体設計の狂いであればちょっとリカバーは難しいのではないか、あるいは取り戻そうとしてコンディションを狂わせてしまうのではないかと心配していたが、杞憂だった。これも課題をしっかり絞り込めたゆえと推察する。下半身は太くなり、膝が適度に曲がり、そしてなにより「片足にならない」。ウルフが敗れる形としてもっと見えやすいのは担ぎ技への対応を誤り(軽々に動いて捌こうとして)、上半身を引き込まれて転がってしまうこと。もう1つはケンケン内股で空転させられ、「めくり」をはじめとした後の先の技を食うこと。これを防ぐために片足の攻撃を減らして両足で進退、背負投は動きで避けるのではなく、下半身で弾く。そして何よりそれが出来るだけの下半身を作る。こういった意識が徹底されていた。
そしてこの「受け」という眼前の課題設定が、結果的にはウルフの本質である「両足を着けた低い進退」にアクセスすることに繋がった。
「両足柔道」こそウルフの本質

ウルフの柔道の本質は「両足柔道」にあると思う。地に足を刷り込むように低く進退し、両足を付けたまま「捩じる」、そして「(胸を)合わせる」。これが我々が持つ、高校時代からのウルフのイメージ(小学生時代はまたちょっと違った柔道だった)だ。内股が得意技とされているウルフだが、長くその柔道を見て来た人には、ウルフが内股の選手だという認識は実は意外に薄いのではないだろうか。内股イメージは後になってついて来たもの。もう少し言えば「ウルフ内股」に代表される技法もどちらかというと返される可能性の少ない、跳ねの要素に頼らない「両足柔道」の系譜に連なるものである。ウルフの迷走は、キャリアの後半に盛った華やかな上積み要素に、手術を経て変質した体が振り回されて芯を見失っていたとも取れる。それが、原点中の原点である核、己の急出世を支えた「低く両足を着けた柔道」に回帰することで蘇ったのが今大会であったと思う。筆者は高校時代、あの「春日のウルフ」がここまで急激に強くなるとは思っていなかったし、低く構えての脇差し、帯持ち、そして「捩じり」と「合わせ」の体幹直接アクセススタイルで上がって来たこともまた大いに意外であった。人が爆発的に伸びるのは、潜在的本質と方法論が噛み合ったときのみ。急出世したということは、ウルフの「本質」とはあの低い進退、徹底した「二本足柔道」にあったということになる。今回立ち戻る場所は、間違いなくここであった。
少し話が逸れるが。「内股の抑制」のほかにウルフの二本足柔道の徹底の端的な表れであったのが、前述「刈り開く大内刈」。序盤から、常のように刈り上げるのではなく、足を着いて「開く」形を徹底していた。思い出されるのは、東海大浦安高時代に演じた佐藤和哉との2試合。3月の全国高校選手権で佐藤に大内返を食らって敗れたウルフは夏のインターハイで佐藤に、なんとまさに大内刈でリベンジ。この時に使ったのが「返されにくい」(筆者は当時のウルフに同日直接この話を確かめている)足を着くように刈り開き、体の中心線で押し込む大内刈だった。「低く両足」がウルフの原点であったことを思い出させるに、これ以上の技はない。
この大内刈に関して答え合わせをせんと、試合後囲み取材に走ってウルフ選手に直接質問してみた。やはり見立て通り、返される可能性が少ない「開く」大内刈を主戦武器に据えての低い進退を意識したとのこと。そしてこの点には、東海大浦安高の恩師の竹内徹氏が4月から東海大の師範に就任、直接アドバイスを受けられるようになったことが大きかったとのこと。迷ったときに、教え子の本質がなんであるかをよく理解する恩師が側にいてくれたことは大きかったと思う。
そして、「眼前の課題設定がウルフを、自身の本質にアクセスさせた」あるいは「迷ったときに教え子の本質を理解している恩師がいてくれた」と書いて来たわけだが、やはり大きく見て、ウルフ最大の長所である「自己理解」の深さが土壇場で本人を助けたということだと考える。ウルフの技や方法論が己の体型や長所に極度にカスタマイズされたものであることは広く知られるところ。今回ウルフはこの最大の武器を何か新しいものを盛る方向ではなく「己のもっとも強い部分は何か」という本質を見つめなおすことに振り向けたのだと思う。ウルフの凄さを改めて感じさせられた己の本質へのアクセス。「刈り開き大内刈」と「内股の抑制」、そして「刷り込むような低い進退」であった。
準備、遂行、判断、素晴らしかった戦略面

ウルフもう1つの特徴である戦略・戦術面も素晴らしかった。準決勝のヴァルラム・リパルテリアニ(ジョージア)戦はこれまで通り明らかに後半勝負志向。徹底して「動的膠着」を作り出し、しかも能動的に試合を動かして、ただの1つも「指導」を失う気配がない。結果、このまま終盤まで持ち込まれては危ないとみた組み手の名手リパルテリアニが過程を飛ばし、首を抱える「両襟奥」で一発勝負。これぞウルフが待ち望んだ、相手の体幹に直接アクセス可能な接近戦である。この展開を逃さず、決勝点となる大内刈「技有」を得た。スコアタイムはまだ終盤突入前の2分31秒という意外な早さ。ウルフに後半勝負を許すこと自体がそもそも危うい、という相手の焦りを呼んだ見事な進退、そしてチャンスを逃さぬ戦術眼だった。

チョ・グハン(韓国)との決勝も素晴らしかった。苦手のチョに対し、得意の押す(担ぎ技を食らいやすい)柔道を捨ててどっしり進退。そしてケンカ四つのチョに対し、釣り手一本から浅い左内股や左大内刈、そこから釣り手側(右)への肩車という連続技を続ける。が、どう見てもこの肩車は掛からない。そしてウルフは明らかに「掛からない」こと自体を呑んで敢えて仕掛けている。筆者は「たとえ手数稼ぎであってもこの先の技がないときついはず、もう1つ先の技を最後に繋げて来るのではないか」という見立てと、もう1つ、「釣り手側に餌を撒き続けている。勝負は順方向ではないか」という予想を候補として持った。ウルフはこの釣り手一本がベースの右側の攻防を、鏡合わせとなるチョの左一本背負投を捌きながら、ひたすら、しつこいくらいに続ける。戦線は徹底的に釣り手である。

そしてGS延長戦、ツト、組み立てを変えて引き手から、それも上腕を深く持ち始めた。潮目が来たようだ。思わず腰を上げた。順方向へのアクセスが始まった。チョは嫌うが、ウルフは続く展開でも引き手で上腕を深く持ち、明らかにこれは意図的。チョはさらに嫌がるが、あの「片手交換」の泰斗であるチョが、もはや疲労し切ってこれを切り離すことが出来ない。この「作り」に要した時間実に9分35秒。すべての鎧をはぎ取られたチョはウルフに体幹へのアクセスを許し、決着の大内刈「一本」。
苦手のチョに、敢えて己の得意な「押し柔道」を捨てる引き算、逆に己の本質である「低い進退」というベースは絶対に変えず、相手のスタミナを奪うための推進エンジンとして選んだ技は釣り手一本ベース、つまりは左一本背負投のあるチョがそこに棲むことをひとまず受け入れてくれる形。受け入れられる形であるがゆえにチョはひたすらスタミナを削られ、そしてウルフは機が熟したと見るや迷わず組み手を両手に変更、それも中途半端に変えるのではなく(段階的に組み手のレベルを上げれば追走を許す)、一気に体幹にアクセスする「引き手上腕」持ちという最も強い形をいきなり採った。終着点としての大内刈「一本」フィニッシュは、もはや必然であった。
この日の100kg級は、これが本当に五輪かと思われるような華々しい撃ち合い(私たちが知る五輪柔道競技はもっと悲壮感があるものだ)の連続。各選手それぞれが己の柔道を表現した、見ていて実に楽しい1日だった。その「祝祭」のまとめが、己の長所を表現し切ったウルフの「一本」であったことはまことに論理的であったと思う。ウルフアロン、五輪金メダリストにふさわしい戦いぶりであった。その勝利を心から祝福したい。
(了)
スポンサーリンク