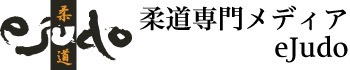文責:古田英毅
Text by Hideki Furuta
キャリア最高の試合を披露した渡名喜

日本代表・渡名喜風南(パーク24)の出来は素晴らしかった。過去最高と評して間違いないと思う。高い運動性能の一方で組み手に粗さがあった渡名喜が、この日は組み手、足技、担ぎ技、寝技を継ぎ目なく連動させた完成度の高い柔道を披露。柔道のレベルが一段ではなく、二段も三段も上がっていた。目を見張った。
出色だったのは準備力、特に白眉であったのはビロディド戦の戦略。挙げきれないのだが、まず唸ったのは大きいビロディドに対して小さい渡名喜がまず釣り手から持って柔道を始めたこと。普通に考えれば相手の釣り手がフリーになるこの入りは奥襟を叩かれる恐怖があるはず(実際に1度思い切り叩かれた)のだが、釣り手から先に持って、極端に接近して体を相手に預けると、実は相手は奥襟を持てず、肩越しのクロスグリップに腕を差し入れるか、正位置(前襟)を持つしかない。腕の長いビロディドなら尚更である。これが嵌った。しかも渡名喜にとってこれはあくまで入り口。抱きつき大内刈、体側をつけての袖釣込腰様の崩しと対クロスグリップ用の手立てを、それも相当有効な解をいくつも準備していた。面食らったビロディドがペースを戻そうとまず引き手で袖を掴んでくれば、迷いなく肩車に飛び込んであっという間に無力化。そしてプラン通りにGS延長戦に持ち込むとスタミナに難のあるビロディドの集中力は明らかに削げる。ここで小外刈と担ぎ技を連動させて圧を掛けると、ビロディドは巻き込み技の掛け潰れ一択。審判はこれを攻勢とみなして渡名喜に「指導」を与えたのだが、渡名喜はまったく慌てず間合いを詰めて誘い続ける。ビロディド幾度目かの払巻込を放つもこれだけ間合いを詰められては十分な回転は出来ず、威力が出ない。渡名喜は崩れず、一人半身で倒れた相手の腕を掬い、跨ぎ、胸を合わせて押し込み、横四方固でガッチリ抑え込む。こうなるとビロディドはまったく動けず「一本」。プラン、手札、シナリオとすべてが完璧に嵌った一番。僥倖に頼らず、偶然を待たず、自ら試合を動かして相手を嵌めた、信じられないほどの完勝だった。

渡名喜は実に落ち着き払った立ち振る舞い。勝ってもこれが当然とばかりに冷静そのもの。優勝することを「仕事」と腹の底まで信じ切った、強者の態度だった。
決勝のディストリア・クラスニキ(コソボ)戦も見事だった。クラスニキの生命線は引き手による袖の把持だが、渡名喜はこれを「持たせない」ジリ貧プランではなく、「自分が持つ」能動的な作戦で潰した。ご存じの通りケンカ四つにおける引き手の有利不利は2つの要素で決まる。ひとつは袖の外側をどちらが持つか。もう1つは空間を半分で切って、どちらの側に両者の手首があるか、である。渡名喜は引き手で外側を持ち、己の空間まできちんと袖を引き寄せていた。腕同士は繋がっているが、持っているのは実は渡名喜の側だけ。クラスニキは「切ってやりなおすよりは」とこれに対して対応がやや曖昧。クラスニキが良い投げを打てないまま一進一退の攻防が続き、あとは渡名喜がどう出口を定めるかという段階だった。

ところが、この「一進一退」の攻め合いの中、渡名喜の左小外刈をクラスニキが外したところで、引き手の「手首」がクラスニキの側に寄せられ、逆に渡名喜の腕が伸びた形になってしまう。この試合ほぼ初めて、僅かの時間だけ、それも局所的に生まれた渡名喜の「組み負け」であったが、己の戦いの最前線がこの「引き手の袖の把持」にあることに極めて自覚的なクラスニキはこの隙を逃さない。迷わず飛び込んだ右内股に渡名喜の体側が落ち「技有」、続く寝技の攻防が終わった時点で残り時間は僅か6秒。渡名喜は、万事休した。

冒頭の繰り返しになるが、渡名喜は過去最高の柔道を披露した。何が悪かったのか、と言われても試合が終わったばかりのこの段階で筆者に思いつくものはない。決勝の中盤、「腹包み」から抑え掛けた場面に決め切っていれば、と一瞬思ったが、これは典型的な「たられば」。プランよし、コンディションよし、遂行能力も齟齬なし。今のところは、たった1度だけのチャンスを逃さなかったクラスニキの強さ、ただ1度のチャレンジで過たず渡名喜を投げたその技の威力を称えるしかない。
ただし、間違いなく渡名喜は強くなった。具体的なターゲットを定め、己と相手を考え抜くことで一段も二段も完成度の高い選手になった。試合に文脈が見えにくい選手、成長の方向性がわかりにくい選手というのが筆者これまでの渡名喜評なのだが、これはまったく撤回させて頂く。目標があること、戦うべきライバルがあることがいかに選手を成長させるか、負けの無念よりも、このことを強く感じた女子第1日の戦いだった。それだけ、渡名喜の柔道は素晴らしかった。

成長出来なかったビロディド

3位決定戦、シラ・リショニー(イスラエル)を破って銅メダルを決めたダリア・ビロディドは「礼」を済ますと大粒の涙を流し、試合場を降りるとほとんど号泣していた。間違いなく悔し涙、無念の涙であったろう。思わぬ五輪の延期で、もう1年48kg級に留まらねばならなかったビロディド。173センチの身長を誇る彼女にとって、それはおそらく地獄の苦しみ、気を抜く暇のない節制に次ぐ節制の日々だったのではないかと想像する。この日は予想通りコンディション悪し。「待て」が掛かると畳に座り込んでなかなか立てず、苦しい表情を見せる今春のワールドツアー2大会と同様の絵は、早くも初戦から現れていた。
ただし、ビロディドの敗戦は「減量に無理があった」「コンディション調整に失敗した」というスポット的な因だけで括られるものではない。最大の敗因は「成長し続ける」という現代柔道トップ選手に必須の条件、すべての選手にターゲットにされる王者という立場であればもはや絶対条件であるこの「仕事」が出来なかったことだ。
2018年と2019年の世界選手権に優勝、絶対王者としてこの階級に君臨したビロディドだが、以降の2年間その柔道はほとんど変わっていない。我々はビロディドが試合に出るたびその柔道を紹介するわけだが、この2年間その文言はまったく変わることがなかった。遠間から圧を掛けては長い脚を差し込んでの大内刈で一気に寄せ、耐えられれば内股に切り返し、投げ切れずばバリエーション豊かな「横三角」の蟻地獄で絡め取る。2019年当時のこのプロフィールは、2021年夏のいまでもまったく変える必要がない。実はこれは、海外のトップ選手にはいまやかなり珍しいことだ。どころかビロディドはこの間不調に苦しむあまり、己の柔道の「何が良かったのか」のかを見失って迷走していた。この五輪はようやくその自己像を取り戻し掛けているという段階(少なくとも背筋を伸ばして進退して、かつてのように上背のアドバンテージを強く意識はしていた)であったが、これはあくまで「リカバー」。何かを上積みしたわけではない。ビロディドの柔道は、まったく変わっていない。
ビロディドは全員に研究されていた。それも渡名喜やクラスニキらトップ選手でない「ツアーの常連」クラスにも。そしてこの日は、その変わらない柔道と、明らかに幼さを抱えて故障しやすいメンタルを、ほとんど「舐められて」いた。初戦のミリツァ・ニコリッチ(セルビア)は角度を変えてその技を封殺、ビロディドが消耗した終盤戦は思い切って奥を叩くなどかなりの強気。ビロディドが急加速して抱きつき払腰を放った残り0秒の「技有」で敗れてしまったが、金星を挙げる気満々だった。カタリナ・コスタ(ポルトガル)も、実際に勝利を上げた渡名喜も、ビロディドのやり方はよくわかっているとばかりに冷静な進退。そしてビロディドが彼女らの想像の上を行く戦いを見せて突き離すことは、ついぞ、なかった。
ビロディドのV逸から我々が感じ取るべきは「過酷な減量の末の銅メダル」というドラマでもなければ、「美しすぎる柔道家のメダル獲得」というような安っぽいおまけバリューではない。どんなに強くても、進化する努力を怠ったものが勝ち続けることは出来ない、現代柔道で生き残るたった1つの条件は「成長を止めない」ことだ、という冷厳な事実だ。技術的停滞、幼いままのメンタル、そして見失った自己像(疲労を恐れるあまり「しつこく三角」という己の柔道のエンジンを失ったままの4試合だった)。この状態で銅メダルまで辿り着いた潜在能力の高さは脅威的だが、今回のビロディドは、買えない。
この先は階級を上げるだろう。この身長なら一気に2階級上げてもいいかもしれない。適正体重に上げ、減量というエクスキューズ(変な話だが)がなくなった時こそがビロディドの真価が問われる時。どんな成長を見せてくれるのか、楽しみに待ちたい。
(了)
スポンサーリンク