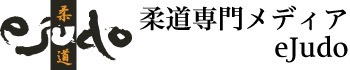大会選定は「空振り」も課題発掘に成果あり、有意義な大会だった

グランドスラム・バクー2025、男子日本代表の「採点表」をお届けする。評価に際してもっとも重視するのは常の通り、「準備」と「実行」の2点。前者は「起こり得る状況に必要な手札を整備して自分の目的を果たすために駆使しているか」、後者は「持てる力を存分に発揮したかどうか」。
まず総評。全日本強化陣、特に男子はおそらく、出発前は頭を抱えていたはず。大会選定が空振りしてしまった。参加人数僅か258名、単純に14階級で割ると1階級平均18名強という小規模大会。しかも海外のトップ選手はほぼまったくおらず、どころか地元アゼルバイジャンですらエース級の投入を渋った。おそらく全日本としてはルール改正1大会目のGSパリは強豪軒並み静観、この大会に重心が掛かるはずと読んでいたのだろうが(判断は妥当だ)、この読みが外れてしまった。“地方の2軍大会”に超の字のつく一線級を送り込んだのだから、結果は見えている。スポーツ新聞やSNSウオッチ媒体は派手な見出しをつけて日本の大勝をあおり、「4年に1度見る層」に対する日本柔道の存在感を上げてくれたが、見上手たちは静か。14階級10階級で優勝という結果は、まったく意外なものではなかった。
ただし、内容面は豊かだった。選手がしっかり仕上げてきたこともあり(大会の状況を考えると逆に切なくはあるが)、上積みと課題がしっかり見えた。全体的には、特に課題発掘の面で意義があったと感じる。選手にとっては次の方向性が明確になった、良い大会だったのではないだろうか。また、大会選定回りでもう1つ言うと、五輪組の復帰戦(角田夏実と阿部詩)としては、ちょうどいい舞台になったと考える。
選考面では、悩ましい。同時派遣で機会の公平性を保ち、かつ強豪ずらりの大会に送り込むことで「リアルに世界で勝てるか」を見定める目論見(例年これがGSパリとGSデュセルドルフという鉄火場で行われていたことを思い起こしてもらいたい)のはずが、階級によってはGS東京とほぼ変わらない、国内2強対決構図になってしまった。かつ、同時派遣の階級はGS東京と結果が逆になった階級が多く、「もうひと舞台」の設定が必須になってしまった。久々、全日本選抜体重別に掛かる重心が大きい年になりそうだ。
続いて各選手の採点に移る。最高点は60kg級の永山竜樹。好調という言葉では収まらない。ひょっとするとここ10年で一番強かったのではないだろうか。
前文:古田英毅
採点・評:eJudo編集部
60kg級
スポンサーリンク