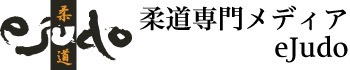文責:古田英毅
Text by Hideki Furuta

大野将平は、いつも少し怒っていた。
定型の鋳型に嵌めてしか己を世間に伝えてくれない我々メディアに。
金メダルという高みを求めれば求めるほど、そしてこれを実際に獲ること自体が、逆に世俗の鋳型に自分を嵌めることとなるジレンマに。
己をわかりやすく「凄い男」だと社会に証明してくれるはずの記号が、逆に己を「金メダルを獲った男の一人」にスケールダウンさせてしまうという構図の矛盾に。
見立てのないwhat質問への丁寧だが「つれない」態度や、東京五輪を前にしたルーティンの「合同囲み」への消極的姿勢、その他数々の言動からこれは容易に察せられた。大野は常に、少し怒っている。これは彼を長く取材しているものであれば誰もが共有する実感であろう。
大野を余人と分けるものに、己に物語を引き寄せる能力の高さがある。勝っても負けても、「自分がどんな物語の、どの位置を担わされているのか」とストーリーを組み立てられる知性と感性がある。高校時代に厳しい判定で負けを押し付けられた時も、すぐさまそれが後年の自分にとってどんな意味のある出来事なのかを解釈・再構築しようとしていたと仄聞するし、チェリャビンスク世界選手権で世界王座から陥落した直後に細川伸二氏から掛けられた「お前はもう強くならん(から試合の勝ち方を考える段階だ)」という言葉を己の転機・羅針盤として繰り返し語ることなどにもこれはよく表れている。その究極は東京五輪直前の2021年7月2日に「THE PLAYERS TRIBUNE」に発表した「“柔道” ~私にはやらなければいけないことがある~」と題する一文だ。
スポンサーリンク