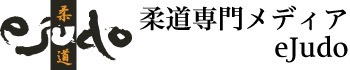文責:古田英毅
Text by Hideki Furuta

コロナ禍の中、選手に質問出来る機会は少ない。五輪代表決定以降数度行われた永瀬貴規の、その数少ない合同取材会で筆者は幾度も「自分の良いところは何だと思うか?」という質問を、表現を変えて繰り返してきた。いや、実を言うと、リオ前から機会あるごとに、地味に聞き続けていた。
理由は2つ。まずはそのまま、筆者にも芯がなかなか掴めない、永瀬貴規のいわく表現しがたい強さを咀嚼解釈して言語化するためのヒントが欲しかったから。見た目極めてオーソドックスな柔道のまま、パワーもテクニックもあり日々技術をアップデートし続ける海外の強豪たちをそもそもの身体の強さで寄せ付けない、階級をまたいだ多くの選手が「組んで一番強いのは永瀬」と証言するその強さの核に少しでも近づきたかったから。もう1つは副次的なもので、日本人の育成の文脈とかけ離れている永瀬の強さがどうやって出来上がって来たものか、そのヒントを掴みたかったから。
2つ目について少し補足すると。読者もご存じの通り永瀬登場前の日本の81kg級は長年苦戦を続けていて、何より体自体の強さで海外勢に負けていた。ただでさえ運動能力・技術・スピードが高い位置でバランスする中量級にあって、このディスアドバンテージはきつい。だから、柔道の組み立ても持ち技も極めてオーソドックスなそれも日本人の永瀬が、鉄骨が入ったような体幹で海外の強豪選手の技を受け切り、弾き返し、そして投げ切る様は衝撃だった。なぜこんな選手が日本から生まれるのか。そして「日本はどうやったらこの先も永瀬を生み出せるのだろう」という問いに自分なりに答えを出せねばと強く思った。筆者が永瀬を初めて意識したのは多くのファンと同様高校1年生時の全国高校選手権。そもそもの立ち姿から他の選手とはまったく違っていた。「鉄骨」ぶりはもう顔を出していた。どうやってあんな体が出来上がったのか、自己評価を聞くことでそれが見えてくるのではないかと思ったからだ。
答えはいつも判で押したように同じ。「組み手」、「相手の嫌なところを突いていけるところ」、「粘り強さ」。こういってはなんだが、これだけ聞くと非常によくある答え、特徴のない強化選手のテンプレ回答だ。実は五輪前の合同取材会ではもう露骨に「小中学校時代はどんな稽古をしていたのか?何を意識していたのか?自分は普通ではないと思った時期があるとすればいつごろなのか?」とかなりまっすぐ聞いてみたのだが、答えは「組み手を意識するようになり、組み手が出来ることで勝てるようになってきた」と、ほぼ同じ。まったく手がかりがつかめない。
永瀬は雄弁な男ではない。これはもうヒントは得られないなと思った。もし本気で答えを得たいのであれば、丹念に、歴代の指導者や周囲の選手の証言を集めていくしか方法はない。考えてみれば本来のやり方はそうあるべきで、こういう選手の「出来上がり方」を本人に聞いて済ますなどというのはかなり怠惰な行為。ここは己(筆者)の思い上がりを恥じるべきである。本気でやるのであれば、五輪が終わってからだ。本題である永瀬の強さの「わかりにくさ」ついても、これは一時放っておいて五輪を見守るしかないと思った。「組み手」「粘り強さ」「相手の嫌なところをついていけるところ」。知りたいのはそこではなく、そうすることで出せる強さ自体の源泉は何かなのだが、これはもう一回忘れておくしかないなと思った。
しかし、今回の五輪、永瀬が語ったその「長所」を意識して試合を観察したことで、実はまさにこの3つが永瀬の勝利のカギであることが良く分かった。テンプレ回答などとんでもない、これがまさしく永瀬の戦いの芯であった。そして筆者が感じていた「わからなさ」自体が、実は永瀬の勝利に大きかったと見る。
「猛獣の狩り」、永瀬の勝因を考える

永瀬の5試合は、ご覧になった通り「猛獣の狩り」であった。いきなり飛び掛かることはしない。逃がしてしまったり、噛みつかれ返すようなリスクは負わない。ひたすら獲物の半歩後ろを歩き続け、相手の牙の届かないところから間断なくプレッシャーを与え、歩かされ続けた獲物が疲労し切ってもはや抵抗出来なくなったところで、初めて飛び掛かり、そして仕留めることを続けた。初戦のヴェダット・アルバイラク(トルコ)などは襲い掛かってさえ貰えず、まったく力を出せないままGS3分16秒「指導3」で終戦。出来ることが何もなくなってしまったほとんど「疲労死」の体であった。ここからクリスティアン・パルラーティ(イタリア)を3分58秒足車「一本」、ドミニク・レッセル(ドイツ)をGS2分36秒谷落「一本」、マティアス・カッス(ベルギー)をGS2分48秒背負投「技有」、そしてサイード・モラエイ(モンゴル)をGS1分43秒体落「技有」。いずれの相手も永瀬のプレッシャーの前に気力体力を削られ、ペースを失い、その上で永瀬の振るった刃の前に沈んだ。
「絶対に負けない」「確実に勝つ」という命題に沿って採った作戦であったが、これに本人が挙げた「良さ」が実に嵌っていた。永瀬は単に体力比べに勝ったわけではない。組み手を僅かにずらし、持ち返し、懐で捌き、長い腕と強い体幹を利して常に相手の力が伝わらず、己の力のみが利く状況を細かく作り続けていた。組み手の彼我の差は見た目の絵面より遥かに上。組み勝っているのは常に永瀬のほうだったと言っていい。派手に組み勝っていないのに、お互いが持っているはずなのに、力を伝えられるのは永瀬の側のみ。見た目は五分五分でも当人にとっては7-3、8-2、そして技を仕掛ければ仕掛けるほどそれがわかってしまう。力をぶつけても伝わらない。おそらくこういうタイプの「強さ」はいまの海外選手にとって一番わかりにくく、しかも研究しづらい。現在の国際柔道の主流は間違いなく伝統的な欧州スタイルで、奥を掴む、あるいは密着した状態から腰をぶつける直線的なパワーファイト。もちろん組み手も技も日々アップデートされているが、「こうすれば伝わる」という力の伝導の道筋、大きな法則は変わりがない。たとえ背を抱いてほとんど結手するという最も強い形を作っても、腹の上でわずかに肩をずらして力を無力化してしまう永瀬のようなタイプはその土台を揺らがせる、もっとも理解し難いタイプなのではないだろうか。この選手がしかも階級ナンバーワンクラスの体幹を持ち、返し技も得意。そしてひたすら組み勝ち続け、半歩後ろから目を光らせるだけで「来てくれない」。乾坤一擲返し技狙いの投げ合いを挑もうにも、一発勝負のチャンスなどまったく与えてくれない(アルバイラクはまさに最後の勝負すらさせてもらえなかった)。そうこうしている間にも、細かく小さく自分は組み負け続けて、「とりあえず掛けなければならない」プレッシャーを食らい続ける。これは、きつい。
また、永瀬の欠場が長く、事実上のニューカマーであることも良かった。世界選手権は2017年以来未出場、2019年夏に国際舞台に本格復帰したが81kg級世界に「馴染む」前にコロナ禍が襲い、以降の1年半に踏んだ国際大会は今年3月のグランドスラム・タシケントただ1回のみ(この間6回のグランドスラムにワールドマスターズ、世界選手権が行われ、主要選手はがっちり試合に出続けている)。誰と誰がどう戦い、その内容が次にどう繋がるかというストーリーが極めて重要な81kg級世界の「文脈」に取り込まれないまま五輪を迎えることが出来た。どっぷりこの文脈に浸かってワールドツアーをウォッチしている我々ファンからしても、実は「永瀬がいる」この大会はかなりレアで特殊な世界。このガッチリ組みあがった81kg級世界に突如降り立った永瀬という「系列の違う」強者が、極めてわかりにくく、研究し難い「長所」を最大限に押し出して来た。永瀬のロウな強さはもちろん大前提だが、その存在がレアなものになっていたこと、しかももっとも嫌な「わかりにくさ」の部分を押し立てて勝負したこと。これは、効いた。出来上がった世界観が強固だからこそ、永瀬の特殊性は大きな武器になった。力が力を制する男子最激戦区・81kg級にあって本番で立ち現れたこの構図。その戦略まさに正解、「嵌った」というしかない戦いぶりだった。
「猛獣の狩り」にはデータの裏付けがあった

永瀬が採ったこの戦略に、データの裏付けがあったということにも痺れた。筆者はJSPORTSの仕事で金メダリスト9人全員にショートインタビューを行う幸運に恵まれた(全員が驚くくらい的確な語彙で、興味深い話を聞かせてくれた)のだが、この際、永瀬は科学研究部から今大会の「指導」の遅さが数字として上がって来ていたことがこの戦略決定に大きかったということを語ってくれた。前日の73kg級までの戦いはどの階級も「我慢比べ」、我慢に我慢を重ねたその先に新たなステージが見えてくるという展開がトーナメント全体を覆っていたのだが、この81kg級はこういうちょっと悲壮感漂う様相とは打って変わった派手な撃ち合い。一種祝祭感すらあるその展開にあって、永瀬が周囲に惑わされず前日までの日本選手の流れを受けた「我慢比べ」に戦型を定めたことには、データの裏付けがあったわけである。
また、永瀬この日の戦いにおいて「半歩離れた並走」とともに大きかったのはその決め技。準決勝と決勝で見せた低い体落(※準決勝の公式記録は背負投だが、体落様に外足を出す技法だった)は特に印象的であったが、これは新たに持ち込んだ技術。これも、データをもとにコーチから「低く潜る技」を提案されて開発した技とのこと。春の時点ではまだ出せなかったとのことだが、これがしっかりモノになっており、五輪本番の土壇場の決め技として見事に開花した。
己の長所と大会傾向を十分踏まえた持久戦戦略、これを具体的に可能ならしめる技術、そして一発本番に絶対必要な「新たな上積み」によるフィニッシュ。実は3月に左足首を脱臼して6月まで乱取りが出来ない状態であったそうだが、準備、戦略、実行とこれしかないという戦いだった。81kg級の面子をいま一度眺めるに、よくぞこのメンバーで日本人が優勝出来るものだと、改めて感動を覚える。永瀬、会心の金メダル獲得劇であった。
あとは「永瀬貴規の作り方」。あの異常な体幹と足腰はいったいどうやって出来上がったのかという一大命題が残る。日本の今後の育成に極めて重要なトピックの気がするのだが、これは当然ながら現状筆者の手には余る。それこそ科研に乗り出して欲しいところである。永瀬を助けた分析力で、今度は彼自身を腑分けして欲しい。本格的な研究があらんことに、期待したい。
スポンサーリンク