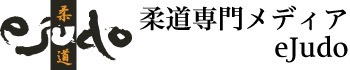(2021年9月24日)
文責:古田英毅
Text by Hideki Furuta
「持って、投げる」を追求し続けた大野

大野将平、見事五輪2連覇なる。「二本持って投げる」という己のポリシーに対して、そしてこれ以上ないほどシンプルな「持てれば」という条件節と「投げる」という帰結節に対して、ありとあらゆる角度から貪欲にアプローチし続けたこの5年間の集大成と言える1日だった。
大野がこの日、特別に持ち込んだ手立ては少ない。後述するが、引き手襟(両襟の引き手)の割合をいつもより増やしていたことくらいだと思う。この「本番用のスペシャル」の少なさに、逆説的に大野この5年間の、執念という言葉では表現し切れない激しい研鑽が透けて見える。大野はこの1日のために、この日絶対に勝つために着々準備を積み、肉体・精神はもちろん技術的な準備を既に終えていたということだ。
二本持って投げる、という言葉はシンプルだ。柔道ファン以外の視聴者にとっても「大野は組めれば、投げる」というこの構図は非常にわかりやすい。だが、ものごとの仕事量の総和というものは実はそう大きく変わるものではない。何かがイージーに見えるとき、当たり前に見えるときには、裏にはそれを引き受ける膨大な労(知的にも肉体的にも)がある。

「組めれば」。日本にあまた存在する「二本持てば投げられる」ことを自任する本格派選手の「持てば」の範囲は実はかなり狭い。極端な場合は、強化選手に近いものでも「袖の外側と、高い位置の釣り手(後襟・横襟・背中)」のみだったりする。本格派選手の試合が「持たせてもらえない」ことを前提に進めざるを得ないことを考えれば、これはかなり狭い。ピンポイントと言って差し支えないくらいだ。そして大野は「二本持って投げる」という分野では世界一の選手、ゆえに相手の「持たせない」警戒も当然ながら世界一。例えば「袖で肘の外側、釣り手で奥襟」というようなピンポイントで掴んで進退できる可能性は極めて少ない。持ったが最後、相手は過剰反応してすべてを捨てて切り離すか、反則覚悟で自ら潰れて試合の進行を止めてしまう。世界一の投げを持つ大野だが、当然ながら持てなければその技は意味がない。大野はまずこの「持てば」の間口を広げ続けた。引き手は内中袖・肩口・脇下・上腕・袖口・襟、釣り手は前襟・横襟・後襟・背中・脇下・肩裏。どこを持っても投げに移れる。こうなると相手は近づくだけで大野と「組まれる」。体を連結されてしまう。まるで鳥黐(とりもち)だ。準々決勝、大野に抗するには超接近戦で体を包んで体格を生かした捨身技に打って出るしかないと接近を試みたルスタン・オルジョフが、その過程で大野に捕まえられ続け、結局はすべてを切って離れてやり直すしかなかった様にはこの「間口の広さ」が存分に表れていた。しかも大野はこの日、引き手で襟(両襟)というエントリーを徹底していた。引き手襟のメリットは、「持ちやすい」(早く持てる)ことと、相手に力を伝えやすいこと。常であれば内中袖などもう少し投げに向いた持ちどころを探ることも多かったはずなのだが、投げが決まりやすくなるメリットよりも「相手と早く繋がる」(相手に力を伝えて、攻めも守りも安定度を増す)アドバンテージを重視していた。「鳥黐」性が増していたと思う。相手は片手技や一発飛びこみの奇襲技の数少ないチャンスを極限まで削られ、大野の圧を受け続けることとなった。長い試合の中、形上「指導」を食らうことがあっても大野が常に優位に立ち続けたあの展開には、長年にわたるこの条件節「持てば」の強化がある。
「投げる」。当然ながら投げの理合を満たすためにはこの二本のもちどころそれぞれの組み合わせによって体の使い方が変わってくるわけだが、大野はこれを緩みなく追及し続けた。「持てば勝てるのに、出来なかった」選手たちと大野の戦型、そして投げの決まり方を比べるとそれがよくわかる。大野の技は持ちどころを選ばない。厳密にいうと選んでいるのだが、相手にとっては「どこであっても持たれれば投げられる」域だ。
加えて大野はリオ後も、毎年着々と「使える技」を増やし続けた。巴投、背負投、出足払、支釣込足。「使える」から「“一本”を取れる」域に昇華させた技枚挙に暇なし。決勝の決まり技が、もっとも得意とする大外刈の「対」の技である支釣込足であったことはこの姿勢の反映であると思う。(余談ながら。大野は試合直後「最後に自分を救ってくれる技は大外刈だと思っていたが、そうではなかった」とコメントしていたが、やはり大外刈に救われたのだと思う。あの技が決まる直前のシークエンスで、大野が勇をふるって得意の”大外落→大外刈”を繰り出していたことを、我々は見ている。大外刈の残像があの支釣込足に繋がったことは言うまでもない)
「持って、投げる」に加えてもう1つ、大野のこの5年間の眼目を表現する言葉があるとすれば「絶対に負けない、確実に勝つ」だ。これを大野は単なるスローガンでなく、極めてリアルに戦型、そして「投げる」行為それ自体に厳しく反映し続けた。投技の、「返される」あるいは「逃げられる」リスクは最小限。大外刈であれば、いったんノーステップで刈り足を着いて両足で踏ん張り(大外落)、足を抜こうとした相手が片足で重心を移したもっとも弱いタイミングで刈り込む。内股であれば空中に置いたまま「詰める」ことで隅落を封じたまま投げ切る。ちょっと脇道に逸れるが、大野のこういった技法の多くが、重量級相手の稽古で磨かれたことであることも興味深い。後述する額支点の内股も大型選手を投げ切るために開発されたものだ。肉体の錬磨が、具体的な技術として結実していた。
もう書き切れない。きりがない。本来大野の技術は筆者ごときが喋々する域ではなく、またおそらくTV中継で穴井隆将氏が濃く解説してくれているであろう(一通り書き終わったら筆者も録画を見るつもりだ)はずでここでいまさら触れるのは僭越なのだが、区切りとして、少しだけ、大野の凄さをまとめておきたかった。勝つべくして勝った、得るべくして得た2大会連続の金メダルであった。
国民が見つめた「詰め」の仕事

大野が技術はもちろん、精神的・肉体的な超人であり、勝つべくして勝った男であることは今更書くまでもない。当日筆者は大野の強さ自体に感動したことはもちろんだが、同時に、もはや勝ったこと自体よりも、この大野2連覇という「現象」の価値について感じ入ってしまった。
国民が、ここまで位相の高い修羅場で、これほど「強さ」に感情移入して、我がこととして必ず勝つというミッション、「詰め」の成功を体験したのは稀有なことではないだろうか。大野が飛び抜けて強いことは誰でも知っている。しっかり力を出せば必ず金メダルに届く力があること、金メダルを獲るに最もふさわしい男であることを前提条件としてしかと承知している。「持てば、投げる」という勝利の条件とゴールも十分理解している。そして柔道競技が「対人格闘技」という不確定要素極めて大きく、かつ万が一『一本』取られたらすべてが終わってしまうサドンデスゲームであることも、そして日本伝統の「持って投げる」スタイルが、手数で「指導」を掠め取るという手段に対して意外に脆い、美学とルールが決してバランスするとは言えない難しいゲームであることも、暗黙知的に知っている。
その中で、依り代として「絶対に勝つ」行為を代行する。もっとも力のあるもの(つまりはもっとも相手に「消す」ことを狙われるもの)が、五輪という不確定要素の石がゴロゴロ転がっている大舞台で、「確実な仕事」を遂行し切り、これを我がこととして体験させる。下手をすると、これは全スポーツジャンル通じて山下泰裕さん以来のことだったのではないか。日本人はいったいに仕事のレベルを上げること自体は得意だが、「詰め」が苦手だ。その皆が息を詰めて見守る難しいミッションを、長い「相手が持たせて勝負してくれない」見た目理不尽な難しい時間を経て、すべての人が期待したゴールである「投げ」で決める。もっともやりたい、もっとも難しい仕事を体感させる。ファンの琴線に、もう触れまくった5試合だったのではないか。
また、大野は持ちどころの幅が広い。「持つ」という条件節の成立が素人目にも、最大限にわかりやすかったはず。出て、二本同時に掴む。あそこを持たなきゃ技が出来ないというわかりにくいハードルが少なく、そもそもなかなか持てないという手詰まり自体がない。わかりやすい。掴まれることを極端に嫌う敵役を前に、掴めばどこからでも技が出て試合を決められる大野が冷静淡々と「詰め」を行う。前述オルジョフが超接近戦の一発勝負しかないと背中を包みに掛かるが、アプローチする度に大野に捕まれ、その度に離れ、気持ちが切れていく様など格闘の構図としてすさまじくわかりやすかった。苛々したオルジョフが怒気を発してほとんど殴り掛かるようにしてバチバチ手を飛ばし、しかし果たせぬまま掴まれて逃げ、逆にラフファイトを仕掛けられたはずの大野が冷静そのもの、眼光鋭くにじり寄って相手を下げる様などはもはや一幅の絵。柔道以外のファンにその強さをわかりやすく解説するためのシナリオがあらかじめ存在するかのようだった。(しかも恐ろしいことに決まった投げ2発は、いずれもオルジョフが望んだ「背中を掴む」ことがついに出来た瞬間なのである)。
日本柔道は強い、とマックス思い入れたファンの期待に応えて、脳内の理想を実現させる。金メダル9個という結果を遥かに超えた一般社会への「強さの刷り込み」であったと思う。日本柔道の強さをもっとも国民に知らしめてくれたのは、やはり大野であった。
この項の最後にもうひとつ。筆者はこのところ、「なぜ日本はこれほどまでに勝ったのか、簡単に話して欲しい」という質問(難しい)を受けると、「準備の質が高かったから」と答えることにしている。ざっくり言って今回の日本は、「金メダルを獲るレベルの力を養う」ことではなく、「既に金メダルを獲る力のあるものが、絶対に誤らずにそれを実現させる」作業、研ぎの仕事に5年間を費やしたと言っていい。特に男子はこの色が濃かった。これまでになかったことだ。髙藤直寿に永瀬貴規と、力を持ちながら頂点に届かなかったリオ組の存在はもちろんだが、男子代表全体を覆ったこの姿勢(文化と言っていい)の発信源は間違いなく大野だと思う。日本大勝の象徴、今回のチームの「色」を規定した男は、やはり大野将平であった。
敢えて「依り代」引き受けた王者の自覚
あらためて恐ろしいのは、大野がこの「強さの依り代」という任務に自覚的であったことだ。大野は大会直前にトップアスリート自らが言葉を発信するサイト”The player’s Tribune”でこの五輪に掛ける思いを吐露している。(余談ながら。こういう形がスタンダードになれば、メディアもより真摯に選手に向き合わねばならなくなるだろう。見出しになる言葉が欲しいだけの芯を食わぬ質問や薄い記事などは要らなくなる)

語ったのはふたつの「東京五輪」と複雑に絡まり合う自らの因縁、宿命、そして「柔道」そのものに対する使命感。1964年の東京五輪で日本柔道に負けを味わわせたアントン・ヘーシンク氏が母校の天理大学で武者修行を行っていたこと、指導していたのが天理大の初代師範で東京五輪の日本代表監督であった松本安市氏であること、この敗戦に危機を感じて日本柔道を復興すべく設立されたのがまさしく自身を育てた講道学舎であること。そして己が表現すべきは相手の良さを消し合うJUDOではなく、己の強さを出すことに全力を注ぎ合う古き良き時代の柔道であること、アクセスすべきは1964年東京五輪時の日本柔道でそれを繋ぐ経路こそが天理大で培った柔道であること、その強さを証すことが自身と日本柔道の存在証明であること、さらに表現する場は同じ日本武道館という舞台しかありえないこと。そして、すべての因縁を結びつけるために必要なのが、金メダルであること。
繰り返すが、この言葉が発せられたのは大会直前である。普通の選手であればなるべくそっとして欲しいと願うであろう試合前。もっともプレッシャーが掛かり、ナーバスになって然るべき時期だ。このタイミングでここまで語り、背負い、「古き良き柔道の復興」までを宣言する。敢えて国民の期待を一身に集め、その上で大会に臨む。王者だからこその振る舞いだと感じた。この記事、未読の方はぜひ読んでもらいたい。大野が単なる強者ではなく「王者」であること、単に「1回勝ったもの」ではなく、王者としての使命と振る舞いに極めて自覚的であったこと、そして己に課したものをあの場でことごとく果たしたこと。その「仕事」の凄まじさが改めて身に染みることと思う。
大野の強さ知らしめたシャヴダトゥアシヴィリの死闘
大野の強さをもっとも知らしめたのは、実はこの日一番の長時間試合、間違いなくもっとも苦しい試合であった決勝のラシャ・シャヴダトゥアシヴィリ(ジョージア)戦であった。

2012年ロンドン五輪66kg級金メダリスト、6月のブダペスト世界選手権では待望の73kg級制覇も成し遂げたシャヴダトゥアシヴィリは誇り高い男である。ジョージアはご存じの通り格闘技が極めて盛んで、王者に対する社会の尊敬は半端なものではない(今大会90kg級を制したラシャ・ベカウリを出迎える空港の熱狂をテレビで目にした人も多いだろう)。そしてジョージア柔道のアイデンティティはパワーファイト。日本が「二本しっかり持って、投げて『一本』を取る」柔道を旨とするように、彼らはガッチリ相手を捕まえ、大技で投げ切ることに快を覚える。手練手管自体を良しとしない風潮すらある。
その誇り高き現役世界王者・シャヴダトゥアシヴィリが己を明確に弱者と規定して、周到な大野対策を講じていた。大野研究の粋を尽くし、これに徹し続けた。彼がもっとも欲しい釣り手背中(あるいは上腕)は得て攻めに掛かるのだが、何より重視したのは大野に釣り手を与えないこと。時に両手を使って抑えに掛かり、たとえ己の釣り手の位置が万全であっても、大野が釣り手を得るやいなやすべての可能性を捨てて切り離し、やり直してチャンスを探した。もっとも得意な右大内刈は力比べのリスクを考えてかほぼ封印。繋がっている時間も、たとえ己の大内刈が出せなくても、大野の技を食わない位置取りに徹した。背中を掴んでの捨身技で一発を狙い、前襟からの担ぎ技で手数を積み、GS延長戦になってからは左袖釣込腰から拾いなおしての右一本背負投というテクニカルな技も繰り出して「指導」2つまでをもぎ取った。
その執念自体に舌を撒いた。シャヴダトゥアシヴィリは準決勝でアン・チャンリン(韓国)と総試合時間9分に迫る死闘を演じている。「指導3」の勝利が宣されたときの筆者の感想は「凄い試合だったけど、これでシャヴダは潰れたな」であった。もう大野と戦うスタミナは到底残っていないだろう、相四つ密着志向という戦型からしても意外に早い決着があるのではないか、と。それがあの大接戦、あの粘り、そしてミッションの遂行に徹し切った戦いぶり。素直に感動した。いったいどれだけ大野に勝ちたいのか。どこからその底力は生み出されるのか。五輪金メダル云々を超えて、「大野将平に勝つ」ということの価値をあらためて思い知らされた気がした。テディ・リネールの戦いを見守るフランス人の気持ちはこういうものなのだろうか。筆者は比較的頻繁に「すべての選手にターゲットにされる」という表現を使うのだが、この言葉の重さ、世界中から「狙われる」ということの重みをこれほど感じさせられた試合もない。
今大会、柔道競技個人戦では14人の金メダリストが生まれた。どの選手も強い。だが、大野の強さ、金メダルの価値はやはり他とは一線を画すものだと思う。横一線の競り合いから抜け出したのではない。誰もがどんな手を使ってでも倒したいと思う状況で、そして全国民が強さの依り代として思いを託す中で、全てを正面から引き受けた上で勝ち切ったのだ。井上康生監督が「最強の柔道家」として称えるのは、ただの言葉ではない。まさに本音だと思う。
「頭支点の内股」について

最後にひとつ触れておきたいのが、2回戦のアレクサンドル・ライク(ルーマニア)戦と、勝負どころの準決勝のルスタン・オルジョフ(アゼルバイジャン)戦で決めた大野の得意技の一、「頭(額)を畳に着いての内股」について。
筆者は「大野万が一敗れるとすれば」のシナリオの第一としてこの技による反則負けを挙げていた。逆に言えばそのくらい純実力比べでの大野の敗北は考え難かったわけであるが、これについては数年スパンで危惧していた。長年国際大会ではあまり取られなかったこの反則が適用されるケースが増えて来ている(2020年ごろから増えた印象を持っている)折でもあり、出来ればやらずに済ませて欲しい技であるなと思っていた。
なので、大会後、JSPORTSによる金メダリストインタビューの機を利用して(アジェンダからは完全にはみ出ているのだが)図々しく聞いてみた。あの技は反則を取られないという確信を持って掛けたものか、どうか。

さほど問題のあった場面とは認識していないとのこと。首が屈曲して後頭部を着いた場合には反則になるが、この技は額支点。畳にねじを打ち込むようにして決めにいく技術で、どういう時に相手が(崩れて)ついて来るかは感覚で理解しており、この動き・この決め方で入ったときには反則の取りようがないとの解説だった。金丸雄介コーチともこの技の判定については幾度か話し合っており、その上での判断とのことだ。
また、大野の日常である重量級選手との稽古を絡めて解説もしてくれた。額を着く決めは、もちろん足を高く揚げる行為のバーターによって出現するもの。自分の体格では本来どうにもならない相手でも内股で投げねばならない、そういう世界の中で揉まれ、生まれ、使われる技術なのだと。階級内最長身選手のオルジョフ相手にあの技が決まったのは、一種必然であったわけだ。
というわけで、大野は「取られない」確信と根拠を持って、そして必要性に従ってあの技を掛けていたということになる。
筆者はこの話を聞いてなお、出来ればあの技を仕掛けるべきではなかったとは思っている。大野の話は正しく、まっとう。ただIJFは年々危険な「形」へのアクセス自体に厳しくなっているし、本番で審判員が常とは違う心持ちでミスを犯すかもしれない。彼の「絶対に負けない」ポリシーからすれば、他人に勝敗を委ねる要素は極力排除すべきだ。オルジョフが己の頭を指さして「反則ではないか」とアピールした、ああいうことをさせるべきではない。
だが得心した。大野が十分な根拠と論理を持ってこの技を仕掛けたことに、そして大野将平をしてこれを投入せざるを得ないほど、厳しい戦いであったことに。大野はこのインタビューで「9個金メダルを獲ったとは言うが、専門家が見ればどれもギリギリ、極めて小差の厳しい戦いであったことはよくわかるはず」との旨も語ってくれた。勝つべくして勝った、全階級通じてもっとも金メダルの可能性高かった大野にしてこの言葉。いかに厳しい綱渡りを渡り切ったのかが、この「額支点の内股」を通じて見えたと思った。
以上である。それにしても凄かった。筆者も出来ればメモを放り出し、仕事(現場での任務はほぼ実況解説である)を忘れて、ただ没頭して見たかった。せめてこれから、TV録画で、ファンの皆さんの体験を追いかけたいと思う。
(了)
スポンサーリンク